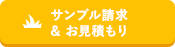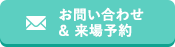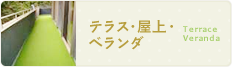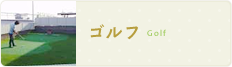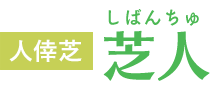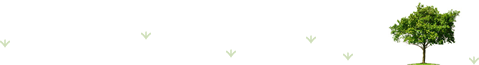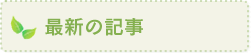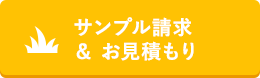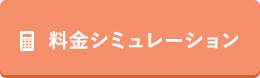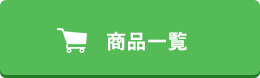家でキャンプ気分

こんにちは。
みなさん「キャンプ女子」という言葉をご存知でしょうか?
キャンプは危険で不衛生で大変ということから男性の主戦場だったわけです。
しかし、実用性のみならずスタイリッシュなデザインのキャンプグッズが増えてきており女性でも取り扱いやすくなってきています。
また、「ゆるキャン△」という漫画が大ヒットをしてかわいい女子がキャンプをすることから、キャンプに対するハードルが下がってきています。
普段とは違うことをすることにより、日頃のストレスを解放し脳を生き生きと活性化できます。
そうはいってもなかなか遠くへ出かけられなかったり、グッズを一から揃えるのが難しかったりします。
そこで家でキャンプ気分を味わうという方法がブームとなっています。
キャンプグッズは防災グッズとしても使えるので、そういったものは取り揃えておくといいと思います。
LEDランタンは防災グッズとしてもキャンプグッズとしても便利に使えます。
テントも一つ持っておくと役に立ちます。
ガスバーナーも防災グッズとして使えます。
いつでもどこでもお湯が沸かせる、温かいものが食べられるというのは災害時においてこれほど心温まるものはありません。
こういうグッズを日頃から使っておくといざという時に焦らずに済みます。
庭のある方は庭に、ベランダが使える方はベランダに、何もない方は室内にテントを張ります。
これだけでもかなり非日常感が出てきますね。
ベランダや室内の場合は演出として一工夫します。
硬い床にテントをのせると、床の冷気が伝わってきてしまいますし、ゴロゴロしようにも硬くてつらいのです。
実際に硬い床で寝ようとしたことがあったのですが、腰が痛すぎて無理でした。

そこで人工芝を使います。
庭に人工芝を敷く場合と違い、ベランダや室内に敷くときは草取りから始まる大がかりな下地作りが不要です。
買ってきてすぐ使うことができます。
現在はクッション性が高いリアルな人工芝が発売されています。
ネットでポチポチしてもいいですし、ホームセンターでもすぐ買うことができます。
見た目は本物そっくりなので、その上にテントをのせると本物のキャンプをしているような気持ちになります。
またインスタ映えもバッチリです。
避難生活の予行練習としても使えるので、一度お家でキャンプ気分を体験してみることをお勧めします。
雑草取りのポイント

こんにちは。
梅雨入りをしてからというもの、ちょっと動くだけで汗だくな日々を送っています。
そうはいっても本格的な夏ではないのでまだ散歩ができます。
一度更地にした場所なのですが、何もしなければ雑草が生えます。
初期のうちは草が横に広がっていきます。
光合成をしなくては生きていけないので、横の場所がなくなると縦に伸びていきます。
そして縦に伸びていける品種が生き残っていきます。
縦に伸びるためにはより深い根を張らなくてはなりません。
マンションの基礎と同じ考えですね。
高層マンションになればなるほど基礎は深くなります。
しっかり根を張ってより高くより強く成長していきます。

雑草取りのポイントは根を深く張る前のごくごく初期段階で根こそぎ取り除くということです。
たまたま、植物園で雑草取りをしている方の声を通りがかりに聞いてしまいました。
これによると
「芝ばっかり見ていると、雑草に違和感を感じてすぐわかるんですよ」
「こうして一つ一つこのピックで取っておかないと、芝が草に負けて成長しないんです」
ということでした。
そして、バケツ一杯に草を取り除いているのが見えました。
プロ仕様の薬を使っているのかと思いきや、雑草の管理は結局こうした地道な手作業の積み重ねということを改めて思い知らされるのでした。
芝ばかり見ているプロだからこそ、ぱっと見で芝のように見えていても、雑草であると認識しごくごく初期の段階で根から取り除くことができるのです。
平日会社員をしていると、庭の手入れは現実的に週末しかできません。
その貴重な週末に腰をかがめて芝と草を見極めて一つ一つ抜いていくということになります。
子供と遊ぶための場所を作るためというものの、草取りで週末を潰してしまうのは本末転倒です。
これから夏になります。
外での作業は熱中症と隣り合わせになってしまいます。
そこで、人工芝が役立つのです。
隙間なく人工芝を敷き詰めると、光合成の場所を奪います。
そのため草が生えなくなるのです。
週末は草取りから解放され、子供と一緒に遊ぶ時間を作ることができます。
これからの季節、人工芝の上にビニールプールを広げて一緒に遊ぶといい家族サービスになりそうです。
なお、プールの底に泥がつかないので、お手入れが楽になります。
こんなはずじゃなかったと後悔する前に

人工芝には多くの利点があります。
一度敷けば10年間草むしりから解放されます。
見た目が鮮やかできれいなまま維持されます。
子どもたちが安全に遊べます。
天然芝とは違い、育つのを待たなくていいです。
そういった利点をフル活用するために一度立ち止まって考えてほしいことがあります。
見た目が鮮やかできれいなまま維持されるためには劣化しにくい素材を買うということです。
「人工」の芝葉になるので、使っている繊維は化学繊維であるということです。
熱をかけると劣化するという性質があります。
また、紫外線という高エネルギー光線を浴び続けると劣化します。
真夏の日差しや熱を繰り返し浴びても劣化しないという素材を選ぶということです。
なお、ポリプロピレンは紫外線に弱く、ポリエチレンは紫外線に強いという性質があります。
「安物買いの銭失い」にならないようにしてください。

10年間草むしりから解放されるためには人工芝を敷く前の基礎になる部分をおろそかにしてはいけません。
まず、「完全に」草を取り除くということです。地上部だけではありません。
地下に張っている根を1本残らず取り除きます。多年生草本は地上部が枯れた状態でも冬を越します。
その間、根はしっかり生きています。この根があるうちは翌年しっかりと地上部を成長させます。
そのため根を含めて取り除かなくてはなりません。そしてその上に防草シートを敷きます。
雑草が生き残る隙を決して与えてはいけません。
そして人工芝を「隙間なく」敷き詰めることが必要です。
隙間があると光が差し込んでいきますので、植物は光合成をします。
その隙間から草がメキメキと生えてくるのです。
人工芝を敷くためには広さによってはつなぎ目ができます。
そこを丁寧にふさぐことが必要です。この作業を怠ると雑草が生えてしまいます。
そこまでできる自信がない方は職人さんの力を借りてください。
ただこの職人さん選びで失敗することがあります。
芝人には本部で研修を行った職人がFC加盟店として活動しています。
人工芝一筋、全国で人工芝を施工してきた職人の技術を加盟店に伝えています。
安心して頼むことができます。
人工芝は足腰に悪い?

みなさん、人工芝はけがをしやすいという話を聞いたことがありますか?
元メジャーリーガーの松井秀喜さんが「アメリカは天然芝の球場が多いので膝の負担が少ない」とおっしゃっていました。
松井さんが海を渡る前の東京ドームは往年の人工芝を採用していました。
東京ドームは、野球はもちろんコンサートにも使う多目的施設です。
コンクリートの上にペラペラの人工芝を張っている状態でした。
外野手だった松井さんはそのクッション性が悪い人工芝の上を走り回らなくてはなりませんでした。
その蓄積が晩年の膝のけがにつながったといわれています。
その後、東京ドームはロングパイル人工芝ちいって、
芝葉が長いものを採用しています。
他の球場でもどんどんこのフカフカ人工芝を採用しています。
しかしながら、往来の人工芝に対するイメージはなかなか払拭できていないのが現実なのです。
コンクリートの上に人工芝を敷くのですが、
コンクリートの印象に当時の人工芝の薄さと相まって
わたしたちに強烈な印象を与えたのでした。

現在主流となっているフカフカのロングパイル人工芝が天然芝と比べてけがをしやすいのか?という研究が行われています。
その一つに、人工芝ピッチにおけるサッカーの試合が筋損傷に及ぼす影響(順天堂スポーツ健康科学研究 第 1 巻第 3 号(通巻15号),414~420 (2010))という研究があります。
土、天然芝、人工芝のピッチの上で大学生サッカー選手が試合をし、その後の状態を調べたものです。
筋損傷を評価する指標の一つであるCKという数値は土が有意に高く、人工芝と天然芝は同じくらいだったそうです。
他の指標であるLDH、アルドラーゼ、Mbにおいても同様で「土>人工芝=天然芝」という結果でした。
人工芝の筋損傷の程度として土より低く天然芝と同程度ということでした。
こうしたフカフカの人工芝は個人の家庭でも簡単に手に入れることができます。
ホームセンターで買うことができますし、楽天市場でポチポチして買うこともできます。
室内に敷いてインテリアとして利用できます。
またベランダに敷いてちょっとした遊び場にすることができます。
庭に敷く場合は注意が必要です。
敷く前の基礎作りが必要です。
基礎作りに不安のある方は職人さんの力を借りることをお勧めします。
緑のインテリアで癒し効果抜群

みなさん「コロナ疲れ」を感じていますか?
厚生労働省による「新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査」が昨年9月に行われました。
これによると何らかの不安を感じている人が半数程度いたそうです。
昨年の緊急事態宣言時では6割の方が不安を感じていました。不安の対象としては自分や家族の感染が6割以上でした。
30代~40代においては自分や家族の仕事や収入の不安がありました。
そして、1年以上こうして不安を抱えたまま生活をし続けてきています。
家にいることが多くなっているため「普段過ごす部屋はリラックスしたい」と思うのは当然のことです。
「リラックス=緑」と思い浮かべる方が多いと思います。
緑は木や森など自然を思い浮かべる色です。
この緑色を目にすると和みを感じることが多いです。
暑さや寒さを感じないため一年中使うことができるという利点があります。
緑が持つ力として癒しやリラックス、人の気持ちを落ち着かせるという心理効果があります。
というのも、自殺の名所だったイギリスの橋の色を黒から緑に塗り替えただけで自殺者が激減したそうです。
普段過ごす部屋に緑色を取り入れるだけでリラックスすることが可能です。
ソファーやカーテン、テーブルや椅子など可能なところから緑色に変えていきます。
黄緑色は明るく軽やかな印象を作ることができます。
一方、深緑色はシックで大人っぽくなります。
クッションは昼寝の枕だったり、腰当てだったり、うつ伏せで漫画を読む時の胸当てだったり普段お世話になっているアイテムです。
あれもこれもできない方は、クッション一つ変えるだけで緑が触れる回数を増やすことができます。

<埼玉県FC 人工芝の芝人 坂戸店 施工>
そして、ラグマット替わりに人工芝を取り入れるというのはいかがでしょうか?
リアル人工芝はクッション性が抜群で寝転がってみるととても気持ちがいいのです。
本物のような質感があり植物に癒されている気分を味わうことができます。
人工芝は「根を張らない」という利点がありますから、部屋の中に置くだけでOK。
お手入れは、ブラッシングと掃除機で大丈夫です。
ここで昼寝をしたら日頃の精神疲労がすっきりできそうですね。
きれいに整備された芝生でも

ちょうど先日のことですが、遠くへお出かけをしました。
近所の公園とは違った刺激が欲しくなりました。
広い芝生のあるところはいいですね。
開放感はもちろんなのですが、鮮やかな緑がきれいで目の保養になります。
子どもが広い場所で安全に走り回れるので、親としては安心してみていられます。
今のうちにしっかり走って足腰を鍛えてほしいと思っています。
これほどきれいな場所を作れるのは、スタッフさんたちがしっかり手入れをしてくれているからです。
よくよく観察をすると、スタッフさんの思いが伝わってきます。
大掛かりなメンテナンスは営業時間にやっていないようですが、毎日の作業をひっそりとやっているのがわかります。
落ち葉拾いに、ゴミ拾いを丁寧にやっている姿を見ることができました。
芝生は生き物ですので、人間に踏みつけられ続けるとダメになってしまいます。
その場所に新しい芝生を植えてそれがしっかり根を張るのを待ちます。
囲いをして人間が入らないようにしなくてはなりません。
人間の遊び場として使う部分と、新しい芝生を育てる部分をローテーションして常にきれいな芝生を作っています。
新しい芝生を買ってくるというコストが必ず発生します。

そして芝の長さを一定にするために「芝刈り」という作業をし続けなくてはなりません。
この作業をすると上への生長が止められます。
そうすると横へ増やそうとする性質があります。
これは生き残るための本能であり、芝刈りによって葉が短くなる分、葉の数を増やして光合成量を維持しています。
芝刈りを繰り返すと密度の高い絨毯のような美しい芝生に仕上げることができます。
これを一般家庭で現実的にできるのか?ということです。
よっぽど芝の世話が趣味の人ではない限り難しいことでしょう。
現在はリアルな人工芝があります。
見た目と感触は本物そっくりですが、生き物ではありません。
そのため、育つのを待たなくていいのです。
遊ぶ場所と育てる場所のローテーションは不要です。
芝刈りも不要です。
クッション性が抜群で安全に楽しく遊ぶことができます。
みなさんも人工芝を使って安全で楽しい遊び場を作ってみませんか?
しとしと梅雨の時期に強い味方

東海地方までは梅雨入りをしていますが、関東地方の梅雨入りはそろそろ近づいてきています。
雨の日が増えてきました。
雨の日は子供を外で遊びに行かせることができないのですが、雨が上がったとしても地面の状況次第では遊びに行かせることができません。
雨で柔らかくなった地面では滑ってしまうことが予想されるので安全に遊ぶことができないのです。
また、泥だらけになって洗濯が面倒になるという親の都合もあります。
「子供は泥だらけになって遊ぶものだ」という意見もあるでしょうが、
乾いた泥ならはたくだけで取れるのでよいのですが、湿った泥は繊維の奥に入り込んでしまうため洗濯機に入れるまでの下洗いが必要です。
ちなみに、綿素材なら「ウタマロ石鹼」のような固形の石鹸を使ってゴシゴシこすればOKです。
化繊の場合はぬるま湯に洗剤を溶かしておいたものに30分から2時間ほど浸け置きをしておきます。
洗濯機に入れるだけではないというだけで面倒に思ってイライラしてしまいます。

もし、庭の泥を完全に封じ込めてしまえばこうした泥汚れから解放されると思いませんか?
砂利を敷く?コンクリート舗装にする?といろいろ考えることができます。
技術の進歩により「人工芝」という選択肢が使えます。
「隙間なく丁寧に」この人工芝を敷き詰めると泥が入ってこなくなります。
現在の人工芝はとてもリアルで痛くないのです。
クッション性も抜群のため、転んでも痛くならずに済みます。
また人工芝には透水用の穴が空いているため雨が降っても大丈夫です。
しかし、「隙間なく丁寧に」というのがポイントです。
少しでも不安があれば職人さんの力を借りましょう。
庭に人工芝を敷くことで、雨の日に泥はねをすることがなくなります。
雨が上がっても、柔らかくなった泥で滑ることはありません。
水はけがよいフカフカの人工芝の上ですぐ遊ぶことができます。
しとしと雨の季節の強い味方です。
水たまりには蚊がいる

休日の午前中、子供と一緒に公園で遊んでいました。
雨上がりということもあり蚊が大量発生していました。
子供はいたって何もなかったのですが、親の方が蚊に5か所刺されてしまいました。
子供には外で思いっきり遊ばせたいという親心があります。
虫についても子供にはある程度経験させておきたいという親心があります。
ありんこを追っかけたり、ちょうちょを追っかけたり、ミミズやダンゴムシをつついたり・・・虫を通して生き物と触れ合い学んでいってほしいと思っています。
しかし、その代償として蚊に刺されて帰ってくるというつらさがあります。
蚊は卵からサナギにかけて1~2週間ほど水たまりに住んでいます。
成虫になると空気中に出てきて1か月ほど生きています。
そして産卵のために人間の血を吸って水たまりに卵を産みます。
蚊は公園の葉っぱで休んでいて、人間がくるとこれでもかと刺してきます。

蚊を発生させないためには庭やベランダに水たまりを作らないことが必要です。
子供の遊具(砂遊び用スコップやバケツ)は外に置かず室内に保管をします。
水やり用のジョウロも外に置きっぱなしにせず、倉庫などの室内に置くようにします。
植物を育てている方は植木鉢のお皿を使わず、こまめな水やりで対応します。
そして、ベランダに水がたまらないように排水溝を定期的に掃除します。
庭のへこみがないように土を増して、平らな地盤を作ります。
職人さんによる人工芝の施工はこの「平らな地盤作り」から始まります。
草が生えていると根の張り方によって土がデコボコしてきます。
それを丁寧に取り除いてくれます。
デコボコを平らにすることで蚊の産卵場所である水たまりを奪うことができます。
さらに機械で押し固めますので、より平らな地盤を作ることができます。
ただ、そのままでは見た目も寂しく、雨や人がその上を歩くことによってふたたびデコボコになってしまう可能性もあります。
そこへ人工芝を敷き詰めていくと、景観良く、再びデコボコになることもなくなるため、庭の水たまりから解放されるのです。
夏はもちろん秋も蚊が発生します。
庭やベランダの水たまりを見直して快適な日々を送りましょう。
憧れの庭付き一戸建ての落とし穴

みなさんは「庭付き一戸建て」にあこがれますか?
中にはその念願をついに叶えた人もいるかもしれません。
念願を叶えて実際に暮らしてみるとどうですか?
思い描いていた生活とどこか違うと感じることがあると思います。
超ド田舎の一戸建てから駅前のマンションに引っ越した時に気づいたことなのですが、一戸建てに住むと何かと「管理・メンテナンス」に追われるのです。
駅前のマンションではこの「管理・メンテナンス」は管理人さんたちがやってくれています。
しかし、一戸建ての場合はすべて自分たちでやらなくてはならないのです。
家以外の場所の掃除をしなくてはなりません。
玄関から外門までの通路はもちろん、駐車場周辺も外壁周辺もやる必要があります。
ほうきで掃くだけならまだしも、雑草がある場所は草むしりもやります。
こういう作業が趣味の人ならいいのですが、そうでない人にとっては苦行でしかありません。

ちょっとした庭があっても、思ったような庭であり続けるためには常に管理・メンテナンスをし続けるのです。
ちょっとした花を植えるとしても花以外の植物は雑草として取り除かなくてはなりません。
そうしなければ花が生きる場所を雑草が奪ってしまうからです。
芝生を植えるとしても、芝生が育つまで見守っているとその間に雑草がポツポツ生えてきて芝生の場所を奪っていきます。
ポツポツ生えた雑草を手作業で取り除きます。
日頃サラリーマンをやっていると日曜日の午前中はこうした草むしりに追われていることが多いです。
除草剤選びを間違えると雑草のみならず芝生もダメにしてしまいます。
こうしたメンテナンスから解放する方法の一つが人工芝です。
何しろ人工の芝ですから芝生が育つまで見守らなくていいのです。
最近はリアルな人工芝が発売されているため、使用感は本物そっくりかそれ以上のふかふか感を得られます。
もちろん見た目もリアルですので鮮やかなグリーンです。
人工芝のメンテナンスは掃除機とブラッシングです。
葉を立たせるようにブラッシングをします。
ほとんどこれだけで大丈夫ですので、作業が軽減できます。
草を科学する

今朝散歩をしていると、庭先で腰を曲げて草むしりをしているのを見ました。
昔ながらの一軒家で、高齢の女性が草むしりをやっていました。
逆Uの字で作業をしているので、絵にかいたような腰に悪い姿勢でした。
一昔前は毎日こうした作業をするのが当たり前のことだったのだと思います。
現在の集合住宅生活においてこうした「朝の儀式」は廃れていっていることと思います。
その一方で管理人さんたちが住人の代わりにこうした草むしりをやってくれています。
よくよく観察をすると1階のゴミ捨て場にきちんと雑草が生えていました。
コンクリート舗装をしてあってもちょっとした隙間があればそこに生息をしてしまいます。
今回発見したのはオニタビラコの仲間のようです。キク科の多年生草本。
中学生の理科の授業を思い出してみてください。
植物の分類で樹皮のないものを草本といい、1年で枯れるものを一年生草本、複数年生き残るものを多年生草本といいます。
多年生草本は地上部が枯れても根は生き残っていてそこからまた成長を始めることができます。
草むしりにおいて地上部だけを取り除いても根が残っていれば取り除いたことにならないわけです。
そこが多年生草本の難しいところです。
植物ですから、「光合成」をしなければ生きることはできません。少しでも光が届けば植物は生きてしまうということです。
コンクリート塗装によって光を遮っていればそこには植物は生えないのですが、少しの割れ目があって光が届いてしまうとそこには植物が生き長らえてしまうのです。
もし、草を根から「完全に」取り除き、その上に光を遮るもので「完全に」覆うとしたら?どうなるでしょうか?草のない世界がくるということです。
それを現実的にやる方法が人工芝を敷き詰めるということです。
もちろんコンクリート舗装でもいいのですが、人工芝にすると「安全に遊べる」という利点が付いてきます。
また、無機質な見た目ではなく目に優しいという利点もあります。
人工芝を敷く作業はご自身でもできますし、職人さんの力を借りることもできます。
なお、職人さんの力を借りれば、草を「完全に」取り除き、光を遮るように敷き詰めてくれます。
人工芝のあるレストラン

ここ数日で急に暑くなってきました。体が気温に追いつかない日々をお過ごしかと思います。
例のウイルスがレストランに蔓延しているのか?
レストランに対する風当たりは日に日に強くなっています。
例のウイルスがまだおとなしかったころ、わたしたち家族でとあるレストランに行きました。
扉を開けると店内に人工芝が敷いてあったのです。
室内にいるのにアウトドアをした気分になりました。
これなら天気関係なくちょっとしたレジャー気分が味わえます。
スタッフさんから「子どもは靴を脱いで遊んでいいよ」と教えてくださりました。
息子は裸足になって店内を行ったり来たりして遊んでいました。
この人工芝はリアル仕様のものだったようで、本物のようにふかふかでした。
2歳児の肌にとても優しいです。
足の裏が赤くなることはありませんでした。
足の裏の傷はありませんでした。
転んでも膝をすりむくことはありませんでした。

店内でたくさん遊んですっかりご満悦です。
そうはいっても2歳児ですので、しばらく遊ぶと疲れてしまいました。
そしてそのままゴロンと横になって寝てしまいました。
人工芝だからこそできることですね。
店内で横になれる場所があるのは親にとってありがたいです。
その間に夫婦の会話を楽しむことができました。
日頃どう考えているのか? 今後どうしていこうか? そういったことを話すことができました。
日頃の子育てで目先のことに追われているとなかなかできないものです。
これも人工芝のあるレストランだからできたのだと思います。
人工芝を店内に敷くだけなので、床面と固定さえできれば簡単に施工することができます。
雨や風が吹くこともないですから人工芝の劣化を気にすることもありません。
芝自体のメンテナンスはブラッシングと掃除機で十分なのだそうです。
ブラッシングでは芝葉を立たせるようにします。
こうすることであのふかふかをよみがえらせることができます。
ホコリは掃除機で吸い取ります。
施工もメンテナンスも簡単にできるのですから、こういうレストランがもっと増えたらいいのにと思っています。
夏へ向けて虫対策

ゴールデンウィークが終わり、いよいよ初夏の陽気となりました。
そしてしとしとの梅雨を経ていよいよ夏です。
ちょうどこの時期は様々な場所で色々な花が咲いています。
見ていてとても気持ちが明るくなります。
それとともに気づけば室内へ虫が入ってくるのを感じます。
虫が増えるくらい過ごしやすいと言えるのですが、そうはいっても虫対策は面倒なものです。
無害な虫もいますが、病原微生物を運ぶ虫だっているのです。
隣人トラブルとはいかないまでも、隣の部屋のベランダが虫の発生源となっていると気持ちがいいものではありません。
ちょうど「緑のカーテン」といって蔓状の植物をベランダで育てている人が隣に住んでいました。
植物の生長とともに日差しを遮ることができます。
そして、二酸化炭素を吸収して温暖化防止になる効果が期待されています。
その一方で、緑のカーテンの陰に隠れて虫たちが大量発生していました。
わたしたちの家にもちょうどその虫たちが入ってきました。
数年がまんすると、隣人は引っ越してしまい緑のカーテンがなくなりました。
すると途端に虫がいなくなりました。
天然の植物は虫を囲い込んでしまうという欠点がどうしてもあるのです。

一方で、緑には癒しやリラックスといった効果があります。
日々ストレスと闘っている現代人にとって家にいるときこそ、こうしたストレスを解放したいのです。
緑のある生活ではストレスで傷ついたわたしたちの心を癒してくれます。
きっとあの隣人は植物を育てることで、日頃のストレスを癒していたのかもしれません。
技術の進歩とともに癒しと虫対策を両立させるアイテムがあります。
それは「人工芝」です。
現在はリアル仕様の人工芝を家庭のベランダに施工することができるようになりました。
人工芝というと硬いプラスチックの印象が強いですが、リアル仕様の人工芝は違います。
本物そっくりに作ってあり、触感はふかふかで優しいのです。色も本物そっくりです。
しかし、本物の植物のように生きているわけではないですから、虫が増えることはありません。
人工芝は、設置する際もプロの技術を使えば10年長持ちします。
これで、みなさんもリアル仕様の人工芝で虫知らずな毎日が送れるようになりますよ。
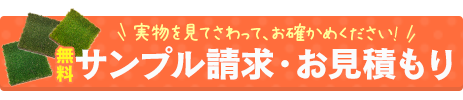
庭の草むしりを楽にする3つの裏技【驚愕】
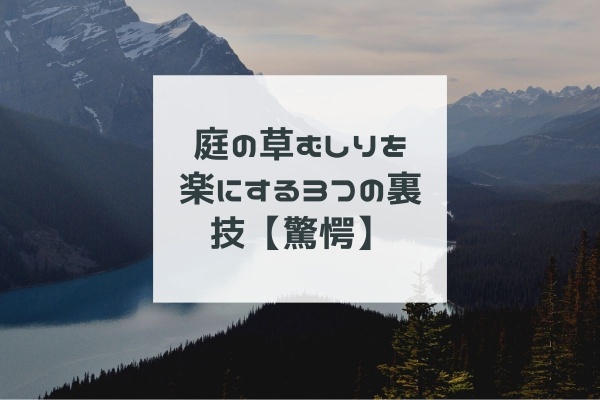
庭の草むしりって目を背けたくなりますよね。とはいえ、みすぼらしい庭のままにはできないから、草むしりをして綺麗にしても数週間後にはまた芽を出し始めます。やってもやってもキリがありません。
そこで、今回は草むしりを圧倒的に楽にする裏技を3つ紹介していきます。
それではみていきましょう。
⑴便利な道具を庭の草むしりで使う
草むしりをしていく中でよく話題になる悩みがあります。
・腰が痛くなる
・時間がかかる
・体力を消耗する
この記事で紹介するのは、これらの悩みを軽減することができるアイテムです。
「大切な庭に薬剤を撒きたくないけど、雑草はちゃんと抜いておきたい。」という方は特に参考にしてみてください。
除草フォーク

上記写真にあるのが除草フォークです。先端が二股に分かれているのを活かして、雑草の根っこ周辺に突き刺し、下から救い上げるように抜きとることができます。
根っこがなかなか抜き取れないような頑固な雑草も、このフォークですんなり抜くことができます。
ホー
ホーはしゃがみ込むことなく頑固な雑草を抜くことができる道具です。作りこそ除草フォークと違うものの、使い方としては前述の除草フォークとほとんど同じ。根っこの下からすくい上げるだけ。
とても便利で使い勝手がよく、腰痛持ちの方には特にオススメの道具です。
⑵庭の草むしりをやめて、人工芝に変える
「雑草が生えない庭が欲しい」
こんなことを夢に見ていた方には、もしかすると人工芝がおすすめかもしれません。
というのも、実は人工芝の庭には雑草が生えてこないからです。
「なんで?どういうこと?」
と疑問を持たれた方のために
・人工芝の庭に雑草が生えない理由
・人工芝には…
という上記2点を解説していきます。
人工芝の庭に雑草が生えない理由
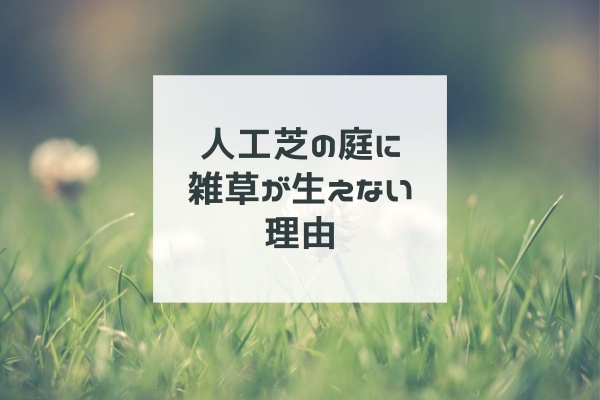
前述の通り、人工芝の庭には雑草が生えることはほとんどありません。
理由はかなりシンプル。人工芝の下に「防草シート」を敷くからです。
防草シートを敷くことによって、雑草の種に発芽する場所を与えず、日光を遮断することで成長の機会を与えません。
とはいえ「絶対に防げる」というモノではなく
・防草シートに亀裂が入った
・壁際(庭の端)に隙間が開いている
などの理由から、発芽し成長する可能性もゼロではないことを覚えておきましょう。
人工芝には虫も湧かない?
雑草と並んで「虫が苦手」という方は多いのではないでしょうか。
そんな方に朗報です。実は、人工芝の庭にすることで虫も湧かなくなるんです。
詳しくは別記事でも記載していますが、前述と同様に防草シートの活躍で虫の発生を防ぐことができるのです。
⑶草むしりではなく、除草剤で庭をきれいにする
しゃがんで引っこ抜いて、集めてゴミに出す…この繰り返しで足腰にダメージがたまってませんか?
もう、しゃがみ込んで雑草を引っこ抜くのはやめましょう。
ここでは除草剤をつかった雑草が生えてこない環境づくりを解説していきます。
除草剤を撒く

「もう、庭の草むしりなんてごめんだわ…」
このように草むしり自体、絶対にやりたくないという方には前述の人工芝や除草剤がいいかもしれません。
すぐに効果があるというモノではありませんが、約半年から1年ほど効果が持つとされています。とは言え注意して欲しいのが、長く伸びた雑草には効果が薄いということです。
あくまで雑草の成長を阻害するモノなので伸びきった雑草に対してはあまり影響がありません。
天然の除草剤?塩を撒く
庭の雑草の根本に塩を撒くことで、雑草から水分を奪い取ることができます。ただしこれに関してはあまりお勧めできません。理由は塩害の原因になるからです。雑草を撃退しても土に塩分が残り、育てたい植物を枯らしてしまうのは、望ましくありませんよね。なので、豆知識程度に留めておいてください。
まとめ
今回は面倒臭い庭の草むしりを効率的に終わらせることが可能な裏技3つを紹介しました。
今回記事を読み進めていただいた方の中には「庭の管理が大変。向いてないかも」という気持ちになってしまう人もいるのではないでしょうか。
もちろん庭づくりは楽しいですが「維持」「管理」は楽ではありません。
だからこそ今回紹介した方法を参考にしていただき、できるだけ楽に、綺麗に、楽しくガーデニングに取り組んでもらえればと思います。
芝生の手入れは大変すぎる】人工芝が起こす大きすぎる変化3つ【驚愕】
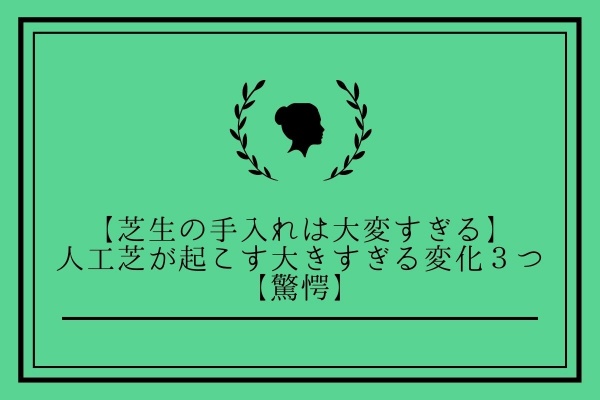
「芝生の手入れってどれぐらい大変なのかしりたい」
「やっぱり芝生より人工芝の方がいいのかな…」
上記のような悩みを持つ方のために、芝生と人工芝の手入れの大変さを比較していきつつ、人工芝を使うべき理由を3つ紹介していきます。
今回の記事では下記の3つの点について説明していきます。
- 天然の芝生をやめると虫が激減する
- 芝生をやめて時間がふえた
- 他人の家の庭の芝生と比べなくて良くなった【気疲れゼロ】
天然の芝生をやめると虫が激減する
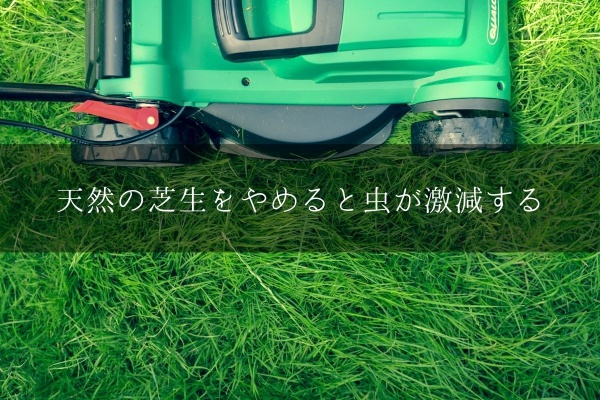
天然の芝生は誰もが知っているように虫たちの温床です。
だからこそ、芝生から人工芝に変えれば虫が激減することを知っておきましょう。
こちらでは下記の2点について解説していきます。
※虫が大好きな方はスキップすることをお勧めします。
- 天然の芝生をやめると虫が激減する
- 芝生をやめて時間がふえた
- 他人の家の庭の芝生と比べなくて良くなった【気疲れゼロ】
見方を変えれば芝生は虫の巣窟
昨今は「虫が苦手」という方は多いかと思います。
おそらくこの記事を見ているあなたも「虫を見るのが好き。
虫大好き。」という価値観ではないでしょう。
ですので、あえてお伝えしますが芝生の下は虫がいっぱいいます。
たとえば梅雨の時期、雨の後。
皆さんはそんなタイミングで庭に穴を掘って頭から突っ込んだことはありますか?
はい、ありがとうございます。
そんなことしませんよね。
見なくてもわかるほどに土の中は虫だらけですので。
つまり何が言いたいのかと言えば、天然の芝生を使ってる以上虫とはバイバイできないということです。
人工芝を使えば虫の数は激減します。
これは人工芝の下に敷かれる防草シートが日光をしっかり遮断してくれるためです。
とはいえ「完全なゼロにする」というわけではありませんが、基本的に虫が住めない環境になります。
この記事を読んでいるあなたが「虫が少ない庭にしたい」ということであれば防草シートと合わせて人工芝を敷くことがおすすめです。
もっと詳しく知りたいという方は合わせてこちらの記事もご覧ください。
芝生より人工芝の方が時間の余裕が増える【手入れが激減】
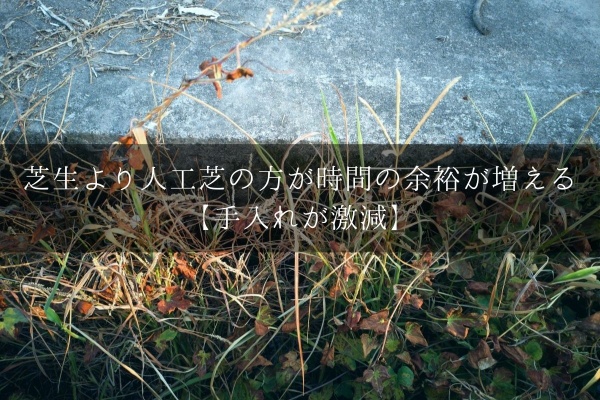
タイトルにもある通り、芝生よりも人工芝の方が圧倒的に手入れが少ないです。
というわけで、ここでは芝生と人工芝の手入れの大変さを比較するために、下記の2点に触れていきます。
- 芝生の手入れ【大変】
- 人工芝の手入れ【簡単】
芝生の手入れは本当に大変で時間がかかります。おおまかな手入れの作業としては以下の3つ
- 雑草駆除
- 芝刈り
- 肥料やり
単純な作業ではあるものの、季節を問わずこれらの手入れを継続するのは非常に大変ですよね。
腰も痛くなりますし。さらには雑草の駆除と芝刈りに関しては1回につき、軽く見積もっても30~40分かかります。
時間短縮に必要な芝刈り機も結構高いですからね。
ちなみに下記リンクの記事から雑草がいかに厄介かを確認できます。
⼈⼯芝は正しく使えば⾍は湧きません。(ゴキブリも)【具体例】
知らない方も多いかもしれませんが、人工芝も実はメンテナンスが必要です。
主には
- 月に数回のブラシがけ
- 猛暑日の打ち水
の二つがあります。
ブラシがけの作業に関しては庭の広さによりますがおそらく数分で終わるかと思います。
目的としては芝葉を立たせること。
そして猛暑日の打ち水ですね。
これは高気温の日や日照が強い日に人工芝の温度上昇を防ぐための作業です。
時間としてはおそらく15分程度。
夏限定の作業ですので。
人工芝を購入する予定のある方はぜひ覚えておいてください。
他人の目を気にしなくて良くなる【芝生のプレッシャー】

芝生と人工芝の違いとして顕著なのが手入れの手間からくる人の目からのプレッシャーです。
ここでは下記の2点について解説していきます。
- 芝生だと人の目を気にしてしまう
- 人工芝なら何も気にならない
芝生の庭は人の目が気になります。
というのも天然の芝生の庭は手入れによって大きく変わるからです。
庭を一面芝生にしているご家庭では「お客さんが家に来る時はカーテンで庭を隠してしまう」という方も多いのだとか。
たしかに、雑草ボーボーで芝の伸びきった庭を人に見せるのは少し恥ずかしいかと思います。
手入れをマメに継続できる自信があるという方であれば人の目が気になることも少ないかもしれませんが。
もはや比較することではないかもしれませんが、人工芝なら人目が気になることもありません。
雑草も防げるし、芝が伸びっぱなしになることもないのでわざわざ庭をカーテンで隠すような必要もなくなるのです。
人工芝ユーザーが年々増加しているのも「人の目が気になるけど、大変な手入れを継続するのも難しい」という方が多いからかもしれません。
まとめ
今回は記事の中で
- 天然の芝生をやめると虫が激減する
- 芝生より人工芝の方が時間の余裕が増える【手入れが激減】
- 他人の目を気にしなくて良くなる【芝生のプレッシャー】
という三つの点について解説していきました。
この記事を読んで、これから庭をどうしていくかについて改めてじっくりと考えていただければと思います。
今更聴けない玄関アプローチの解説【人工芝】
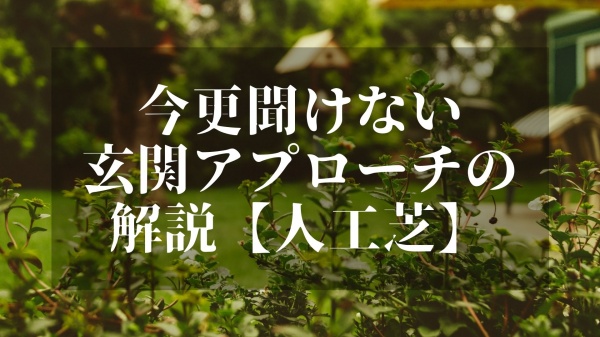
ガーデニングやエクステリアにおいて、玄関先の「アプローチ」が大切ということをよく聞きますよね。
しかし、いまいちピンとこないで
「アプローチって何?」
「おしゃれなアプローチはどんなふうに作ればいいの?」
という疑問を持たれてる方向けに、今回の記事ではその疑問にお答えしていきます。
【 目次 】
玄関までが勝負?そもそもアプローチとは
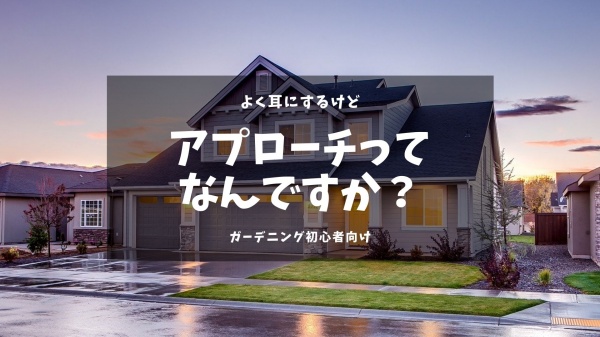
住宅において、玄関までに見る景色が非常に大事ですよね。こちらでは下記2点に触れていきます。
- アプローチとはなんなのか
- 玄関先の印象はデカイ
アプローチというのは家の門から玄関までの道のりのこと。つまり門を開けて最初に目に入ってくる景色です。
門がない場合は敷地に入ってから玄関までのエリアのことを指します。
このアプローチはエクステリア・ガーデニングにおいて非常に重要です。
先ほど言ったように最初に飛び込んでくる景色=アプローチなので、いわば「家の第一印象」のようなものです。
アプローチの見栄えが悪いとこだわりのインテリアにも悪い影響を与えかねません。
例えば、友達の家に行った時に玄関先のアプローチが雑草だらけだったら…「面倒くさがりな人なんだろうなー」のような印象を持ってしまいそうですよね。
雑草のないキレイなアプローチが第一印象になることで悪い印象を抱かれることはないので、できるだけキレイなアプローチを目指していきましょう。
おしゃれなアプローチを作るなら人工芝一択

玄関先のアプローチの重要性を知った上でここではおしゃれなアプローチを作る上で重要な下記のポイントを2つあげています。
- お洒落で清潔感のあるアプローチを作るポイント
- おしゃれなアプローチ
アプローチに芝を使うなら必ず人工芝にしましょう。
「おしゃれなアプローチにしたい」と思ったものの、どうしても
- 芝刈りが面倒臭い
- 雑草の手入れが面倒
- あまり手間をかけたくない
という人が多いようです。確かにアメリカの住宅街のようにキレイな天然芝の庭はかっこいいですよね。でも、毎週芝刈りしてゴミ出し・軍手をつけて雑草の処理はかなり面倒くさいハズ。人工芝はもちろん芝刈りの必要もなければ雑草の心配や虫が湧くような要素もありません。
おしゃれな玄関先アプローチは世界観を崩さない。
おしゃれなアプローチは必ずと言っていいほど庭や住宅の世界観を崩さないデザインになっています。
欧州風の住宅や庭園があるお家であればアプローチにレンガが施されていたり、アメリカ風な住宅ならコンクリート&芝のみのシンプルでキレイなアプローチなどなど。
【人工芝で玄関を彩る。】代表的な人工芝のアプローチ

人工芝は掛け合わせ方や使い方によって出せる雰囲気が大きく変わってきます。
自分の住宅にあったアプローチを作る上で役立つ3つの使い方について説明していきます。
- 飛び石×人工芝
- レンガ×人工芝
- 人工芝のカラーバリエション
和洋折衷な雰囲気を演出できる組み合わせ。
門を開けてから玄関までをいくつかの飛び石で繋いでいるのがこちらです。
この人工芝×飛び石は和洋風住宅で多く使われており多くの住宅で使われています。
また、このパターンはアプローチだけでなく裏庭のデザインなどにもよく用いられます。
欧州の雰囲気が強い組み合わせ。
欧州風住宅の玄関先で多く使われるアプローチのデザインです。
人工芝の緑とレンガの暖かい赤色は非常に相性が良く、鮮やかで見栄えのいい玄関先を演出してくれます。
レンガ自体は段差の境目や人工芝とコンクリートとの境目として使用すると、色鮮やかでおしゃれなアプローチになります。
様々な色の人工芝を使い分けましょう。
アプローチのデザインにおいて「どうしても一面人工芝で統一したい」という方も多くいます。
玄関先のアプローチの部分を道のようなデザインにしようと考えたときに役立つのがブラウンやグレーなど色のついた人工芝です。
緑一色ではなく色を変えて変化を出すことで、人工芝の良さであるフカフカのクッション性は生かしたまま様々なデザインができます。
まとめ
ここまで玄関先のアプローチについて紹介してきました。概要は下記にまとめています。
- アプローチ=家の門から玄関先までの道のりの空間
- アプローチは住宅の第一印象
- 世界観を崩さないアプローチが重要
- 飛び石×人工芝で和洋折衷な雰囲気を演出できる組み合わせに
- レンガ×人工芝で欧州の雰囲気が強い組み合わせに
- 様々な色の人工芝を使い分ける
アプローチは家の第一印象を決める重要な箇所なので、今回の内容を生かしてキレイでおしゃれなアプローチを作っていきましょう。
【注意】人工芝は雑草対策ではありません。

「人工芝を敷けば雑草は生えてこない…って本当?」こんな疑問を持った方向けに下記の3つの真実についてお伝えしていきます。
- 人工芝だけでは雑草を防げない
- 雑草はなぜ生えるのか
- 雑草が生えないようにする方法
人工芝だけでは雑草を防げない
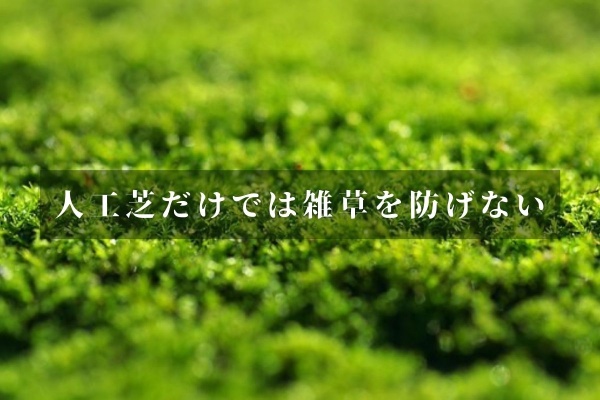
「雑草対策なんて人工芝を買ってきてそのまま敷けばいいんでしょ」
なんて考えだと雑草との戦いから解放される日は永遠にきません。
ここでは人工芝だけでは雑草を防げない理由について触れていきます。
理由は下記の二つです。
- 雑草を防いでくれるのは人工芝ではなく「防草シート」
- 防草シートを敷いていても雑草が生える可能性もある
人工芝の下に引かれることの多い「防草シート」が雑草を未然に防いでくれます。
そもそも防草シートは土に日光が当たらないようにすることで、雑草が好む環境を作らないようにするためのシートです。
敷くか敷かないかでかなり大きな差が出ます。
土の庭に人工芝を敷くときは必ず敷くようにしましょう。
防草シートさえあれば大丈夫!といいきれるわけじゃありません。
たしかに防草シートの威力は非常に大きいです。しかし、
- 雑草の根が取れていない
- 防草シートに隙間がある
- 鳥などの動物のフンと一緒に種が運ばれてくる
などの理由から防草シートを敷いていても生えてくることがごく稀にあります。
なので、万が一にも雑草が生えてきたら「すぐ抜く」これを徹底しましょう。
雑草はなぜ生えるのか
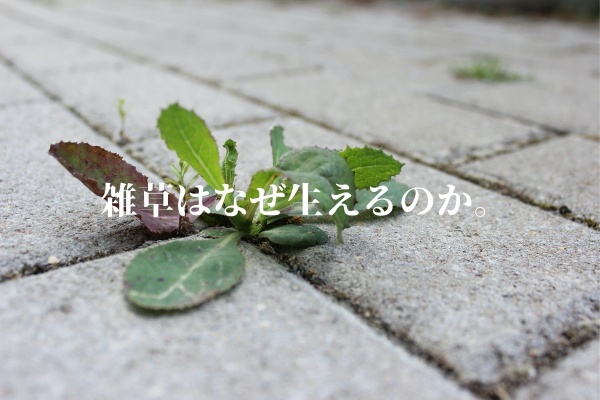
雑草が生えてくるのなんて当たり前のように感じますが、雑草が生えてくるのにもちゃんと「必要な条件」があります。
そんな雑草に必要な条件と雑草が以上に繁殖する理由についてこちらで触れていきます。
雑草が生えてくる理由は下記の3つです。
- 1つの雑草から何万粒もの種がばらまかれている
- 日光が栄養になっている
- 動物が運び込んでいる
実は雑草は私たちの知らない間に何万粒もの種をばらまいています。
なので、人間がタネを巻かなくても少しの土があれば「アスファルトの割れ目」のような場所であっても発芽が可能。
つまり、一つの雑草を抜くだけではダメです。
「雑草が生えないようにする方法」でまとめているように、抜いた後の雑草対策までしっかり行いましょう。
雑草の栄養は日光です。
というのも雑草は主に「好光性種子」という種類の種から発芽するものが多くあり、日光さえあれば発芽して成長します。防草シートが日光を遮断することに長けているのも「好光性種子」に栄養が届かない環境を作るためです。
つまり、日光と少々の土さえあれば雑草が生えてくるということ。
ここまで読み進めると「雑草が繁殖しやすいのは分かったけど、庭で1本目の雑草はどうして生えてくるの?」という疑問が生まれてきますよね。
実は1本目の雑草の種は「何者か」が運び込んできています。
これは「不法侵入者」ということではなく、例えば「猫の体毛にひっついた種」だったり、「鳥のふんに混入した種」だったり、「風で飛ばされた種」だったりするわけです。
雑草が生えないようにする方法

確かに雑草の生命力は非常に強いです。
しかし、ここまでに身につけた知識があれば、雑草が生えないようにするためにすべきことが見えてきます。
ここで紹介する、人工芝の下から雑草が生えてこないようにする2つの方法をしっかり行いましょう。
- 雑草をしっかりと抜く
- 防草シートを隙間なく綺麗に敷く
人工芝を敷く前にしっかりと雑草を抜いておきましょう。
いくら防草シートを敷くとはいえ、できる限り雑草が発生/繁殖する可能性はゼロに近づけたいですよね。
雑草の根っこすら残さないように徹底して「根絶やし」にしていきましょう。
防草シートはちゃんと隙間なく敷くようにしましょう。
思いがけない小さなスキマから雑草が生えてきてしまう可能性もあります。
特に気をつけたいのは花壇のレンガや庭の壁との隙間です。
スキマを作らないように敷くのが少々難しいので気をつけて敷きましょう。
まとめ:人工芝を敷く前の作業を丁寧に行いましょう
今回の記事で触れたことをこちらにまとめました。
- 雑草を防ぐのは人工芝でなく防草シート
- 雑草は少しの土と日光があれば発生する
- キレイな施工と入念な除草作業が効果的な雑草対策になる
せっかく人工芝を使うなら、人工芝を敷く前の作業は少し大変ですが、雑草が生えてこないキレイでラクな庭がいいですよね。
事前の雑草対策をしっかりして最高の庭にしましょう。
【購入前に読むべし】人工芝の手入れは本当に簡単なのか【落とし穴あり】
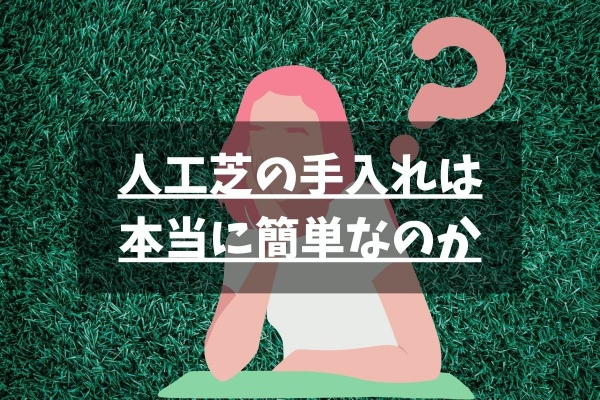
「長持ちさせたいけど人工芝の手入ってどうすればいいの?」
「実際、人工芝ってどれくらい手間がかかるの??」
「手入れが大変な人工芝は買いたくない」
人工芝を選ぶ前にはこんな疑問が頭によぎってしまいますよね?
こちらの記事では上記のような疑問に答えていきます。
また、この記事を読むことで「手間の少ない人工芝」を選べるようになります。
【この記事で伝えたい3つのこと】
- 人工芝のブラシがけと掃除機の頻度について
- 施工がダメだと手入れしても…
- 手入れ要らず?長持ちしやすい人工芝の選び方
人工芝のブラシがけと掃除機の頻度について

人工芝の手入れは基本的に週1回のブラシがけ
人工芝は毎週ブラシがけをして下記3点ができればOKです。
- ほこり取り
- 寝てる芝葉を立たせる
- 様子の確認
特に寝ている芝葉を立たせることが1番重要。
単純に「綺麗な見た目を保つ」と言うのが大きな理由ではありますが、芝葉を立たせることで本来のクッション性を維持したり、紫外線による変な色褪せを防ぐなどの理由があります。
また掃除機は2ヶ月に1回おこなっていればOK。
水捌け用の穴が、ゴミや抜けた芝葉などで塞がったままになると水たまりやカビなどの原因になりかねないません。
施工がダメだと手入れしても…

施工にはちゃんと手間かけましょう
そもそも論ですが、どんなに良い人工芝を買っても、どれだけ丁寧に手入れをしても、施工がダメだと長持ちしません。
人工芝自体が長持ちしなくなりますし、「見た目」や「使用感」に下記のような問題が出てきます。
- 人工芝の下で雑草が繁殖、虫が発生
- 整地不足で人工芝が凹凸だらけ
- 接合部分からめくれてしまう
「こんなはずじゃなかったのに…」なんてセリフを言わないためにも施工はキッチリ、丁寧に。
施工業者に頼むとしても、テキトーに選ぶのではなく、実績があって信頼のできる施工業者を選びましょう。
手入れ要らず?長持ちしやすい人工芝の選び方

人工芝の中にはそもそも短命な人工芝もあれば、品質が良く、長持ちする人工芝もあります。
「でも探し出すのは難しいし、使ってみないとわからないでしょ」
確かにおっしゃる通りで、長持ちする人工芝を選ぶのはむずかしいのが普通。
しかし、主に3つのポイントを押さえれば、人工芝の初心者でも簡単に見分けることができます。
- 人工芝の芝葉の素材
- 人工芝の芝葉の密度
- 人工芝の芝葉の形状
人工芝の芝葉の素材
人工芝の芝葉の素材にはおもに「ポリエチレン」「ポリプロピレン」「ナイロン」の三種類が使われていて、耐久性が強く長持ちするのは「ポリエチレン」です。
ポリエチレンは上記三つの中で最も多く使われている素材で、最近の人工芝の多くはポリエチレン性が占めています。
「ポリプロピレン」はポリエチレンほどではないですが適度な耐久性があり、価格もポリエチレンよりも安価です。一般的に「ナイロン」は耐候性が低いので屋外での使用が難しく、高価なため コストパフォーマンスが高い「ポリエチレン」をお勧めします。
人工芝の芝葉の密度
短いにせよ、長いにせよ、芝葉の密度は非常に重要です。
人工芝において芝葉の弾力性やクッション性というのは命。
糸がスッカスカの歯ブラシは毛先が広がってダメになりやすく、糸が詰まっている歯ブラシが長持ちしやすい。
人工芝を買うときは、弾力性やクッション性に直接関係する「芝葉の密度」の高いものを選びましょう。
人工芝の芝葉の形状
どこの人工芝でも一見同じように見えるのが芝葉の形状。
しかし「リアルさ」や「耐久性」「クッション性」を追求した末に、芝葉の断面が特殊な形状になっている人工芝があります。
例えば弊社の人工芝である「SターフCOOL」がそうです。
断面がひし形に加工されていることで、芝葉自体は裂けにくいため耐久性も強く、クッション性もあります。
まとめ
今回は「手間の少ない人工芝」を選ぶための知識について触れていきました。
ほとんどの場合、人工芝の手入れ自体はそれほど大きな負担ではありません。
しかし「寿命が短い人工芝」や「劣化の激しい人工芝」を選んでしまえば、通常以上の手間とコスト(時間とお金)がかかってしまう恐れがあります。
毎日ブラシをかけなくてもいいように、人工芝選びでは「なんとなく良さそうだから」というような判断はせず、よく考えて選ぶようにしましょう。
【結論】硅砂なんて人工芝には必要ない
「人工芝ってやっぱり砂(硅砂)を入れたほうがいいの?」
・
「なんのために硅砂をいれるの?」
・
今回はこんな疑問にお応えしていきます!
人工芝に硅砂は必要ない
こちらでは下記の人工芝に硅砂が使われる理由について紹介していきます。
- 硅砂が使われるのは芝を立たせるため
- 人工芝がめくれないようにするためのお守り
・
・
・
硅砂が使われるのは芝を立たせるため
硅砂が人工芝の上に巻かれる理由の一つに「安っぽい人工芝は芝葉がすぐに倒れてしまう」という問題があります。
・
なぜこれが硅砂を撒く理由になるのかというと、芝の隙間に硅砂が入り、芝葉が倒れないようになるからです。
・
誤って品質の悪い安物の人工芝を買ってしまったご家庭では、すぐ倒れてしまう人工芝をなんとかするために「硅砂」が使われます。
・
特に最近は大手販売サイトで多くの品揃えの人工芝が閲覧・購入できるようになりました。
・
おかげで人工芝はとても手に入りやすくなりましたが、その弊害として「誤って品質の悪い人工芝を購入してしまう」という弊害が多く起こっているのも事実です。
・
話が脱線してしまったので戻すと、一般家庭の庭やベランダに置いて人工芝に硅砂は必要ありません。
・
必要になるくらい、芝葉の密度が低くてすぐに倒れる人工芝を購入しないように充分気をつけましょう。
・
・
・
人工芝がめくれないようにするためのお守り
二つ目の「硅砂」の役割は人工芝がめくれないようにする「重り」の役割です。
・
基本的に人工芝は「重り」がなくてもめくれないように施工をし、長期使用に及ぶ劣化、予測不能な強風などでもない限りはめくれません。しかし、先ほども書いたように単なる低品質の安物の人工芝の場合、軽いがゆえに起こり得ます。
・
そういった場合には人工芝の上から「硅砂」を撒くことは良い手段かもしれません。
・
さらに前に紹介した「芝の倒れやすい人工芝」のカバーにもなりますので、とりあえずなんでもいいから人工芝を敷きたいという方には「硅砂」は便利なアイテムだと思われているようです。
・
しかし、品質が良くしっかりした人工芝であればめくれることは滅多になく、また、施工もつなぎ目や杭打ちを慎重に行えば、しっかりとしためくれにくい人工芝を設置することが可能です。
・
・
・
硅砂を入れるデメリット
こちらでは下記の硅砂を撒くことのデメリットについて紹介していきます。
- 見た目がオシャレではなくなる
- 費用ががかかる+二度手間
- 雨水が抜けにくくなる
・
・
見た目がオシャレではなくなる
人工芝と言えば綺麗な緑。のハズだったのに硅砂を撒くと、あくまで「砂混じりの人工芝」という見た目になってしまいます。
・
もちろんそれを含めて硅砂を使うのであればいいのですが、見た目のために買った人工芝の見た目のクオリティを自ら下げるのはあまりお勧めできません。
・
・
・
費用ががかかる+二度手間
硅砂の購入にはもちろん費用がかかります。
・
きっとお近くのホームセンターやインターネット上の通販サイトからも購入できるでしょう。しかし金額自体は25kgで3000円以内ほどなので、実際の問題はそこじゃないんです。
・
本当の問題はタイトルにもある通り「二度手間」購入してから人工芝の上に砂を広げるまではいいのですが、その後が大変です。
・
ムラができたら見栄えが悪いので硅砂のために定期的にブラシがけ。人工芝を張り替えるときには硅砂を全て回収してから張り替え。一体、手入れいらずの人工芝はどこへ…(笑)
・
・
・
雨水が抜けにくくなる
人工芝にはもともと水捌けを良くするための穴が無数に空けられており、雨が降っても雨水が抜け、地面に浸透するようになっています。
・
しかし、その上から硅砂を撒くことで穴に砂が詰まって人工芝の水捌けが悪くなってしまうことがあるのです。
・
その結果、人工芝にカビが生えたり、埃が溜まってしまうといったことにもなりかねません。
・
だからこそ、最初から硅砂の必要ない品質の人工芝を買うことが非常に重要なポイントになってくるのです。
・
・
・
まとめ
今回の記事では「人工芝に硅砂を撒くことのデメリット」についてお話ししていきました。
・
ちゃんとした品質の良い物を買えば、手間も少なく、長く保つおしゃれな庭を実現することができます。
・
もちろん中には金額にシビアで「安い人工芝と硅砂の組み合わせ」に頼ってしまう方も多くいらっしゃるようです。
・
今回の記事では、そんな方に品質にこだわり抜いた人工芝を選んだほうが総合的に「メリット」が大きいということに気付いてもらえれば幸いです。
・
最後に・・・
一般的に通常の景観目的のお庭につきましては、珪砂は不要となります。スポーツなど、通常使用以上の負荷が人工芝へかかる場合におきましては、
珪砂を入れて耐久性を増す目的に使用する場合もございます。