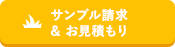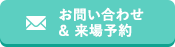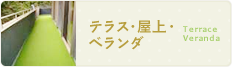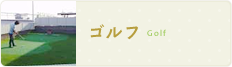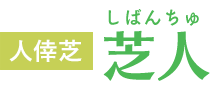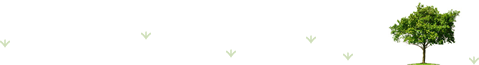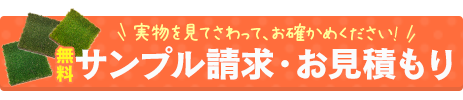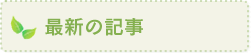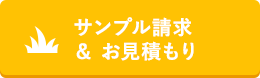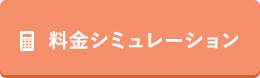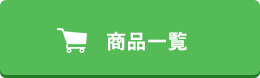本末転倒の庭いじり

せっかく庭のある家を買ったのですから、思う存分庭いじりを楽しみたいと思いませんか?
ガーデニングの中で最も時間と労力を使うのが雑草取りです。
冬になりやっと草がなくなってきたところですが、雑草たちはそれでも根を張って生活をしています。
そして春になりいよいよボーボーと生え始めるのです。
雑草とよく言ったもので、繁殖力と生命力は本当に脅威です。

わたしたちの体力があるうちは雑草の一つや二つ大したことではないのですが、
日々の仕事に家事に育児に・・・となり、そして草取りとなると体の負担が大きくなります。
雑草を抜く作業というのはしゃがんだりかがんだりする姿勢になります。
草の根というのは横にも縦にも広がっています。
そうすると1つ抜こうとしても奥深いところまで根がありますし、横の方にもつながっていて隣の草の方まで抜くことになります。
雑草対策が大変だから庭いじりを止めようかなと思うのも無理はありません。
花や野菜を植えようと思っても、雑草に追われていては本末転倒です。
特に多年生草本の根は本当にしつこいです。
ヨモギ、ヨメナ、セイタカアワダチソウ、ドクダミといった多くの植物は根茎を横に何本も伸ばします。
そしてその先端からさらに子に当たる根茎を伸ばし・・・といったこと何度も繰り返してどんどん横に増えていきます。
1本抜いても根茎が残っている限りまたそこから増えていきます。
根こそぎ退治しないとボーボーへの道が待っています。

<長崎県FC加盟店 株式会社invest 施工>
まずは草取りから解放されなくては楽しい庭いじりをすることはできないのです。
だから一度本気の雑草対策に取り組んでほしいのです。
雑草対策目的で人工芝を敷くという方法があります。
隙間なく人工芝を敷くことで光合成を抑えることができます。
これにより草の生長が止まり地上に生えなくなるのです。
さらに人工芝ならば庭の景観を悪くすることはありません。
きれいな庭で楽しく過ごすことができます。
その上で育てるスペースを作りそこで育てたい植物を育てていくようにします。
冬は本当に草がありません

都市部では落ち葉のじゅうたんとなっています。
それをもふもふ踏んで遊んでいます。
ブタクサが猛威をふるっていた空地はすっかり枯れ果ててしまいました。
寒さを感じるため冬なのですが、あたりの景色もすっかり冬です。
ブタクサはキク科の一年生草本です。こうして冬になると枯れているのが見られます。
近所の空地を見渡すと背の高いブタクサが斜めに倒れて枯れているがわかります。
ようやくブタクサアレルギーから解放されたことでしょう。
しかし、アレルギーを考えるとき「通年性」というのがあります。
この原因はハウスダストです。
ハウスダストに含まれている生きているダニと死んでいるダニが影響しているそうです。
ちょうど、大掃除の時期ですから、家中の掃除をするようにしてください。

そして、外に草がないという利点を最大限に生かす時がきました。
ここで草取りを終わらせてしまいましょう。
今生えている草は多年生草本です。
根を生やして暖かくなるのを待っています。
これを放置しておくとまた春になって草ボーボー生活が始まります。
多年生草本の共通点として「クローン生長」をするという共通点を持っています。
クローン生長とは種からではなくて、自身の断片から増えることです。
わたしたち人間のクローンは難しいのですが、雑草のクローンは簡単にできるのです。
多くの草は根から増えます。
根に栄養器官(ジャガイモみたいなもの)がありそれを使って増えていきます。
また根が横に伸びてそこから新しい芽を出すという方法で増やしていく種もあります。

<千葉県FC加盟店 有限会社グリーンフォエバー施工>
草のない庭を作るための方法として人工芝を敷く方法があります。
土づくりにおいてまずやる作業が全ての草取りですから、この冬にやっておくと非常にスムーズに進めることができます。
その草取りが終われば土をならして、その上に防草シートを張ります。
この防草シートをしっかり張ることで光合成を抑えることができます。
そうすれば春になっても草ボーボーになることはありません。
しかし、防草シートのみの庭では草が生えなくても土地の活用にはなりません。
人工芝を張ることで土地活用になります。
人工芝の上で遊んだりすることができます。
冬の宝石を家に作る

都市部では毎日落ち葉拾いです。
朝晩の冷え込みが強くなってきましたね。
毎日寒いですが、この季節ならではの「楽しみ」があります。
それがイルミネーションです。
光は水蒸気があると水分子に当たって散乱してしまうため、透過率が下がります。
冬のように気温が低くて乾燥していると、空気中に水蒸気をため込むことができないため光の透過率が下がります。
また日が沈んで早い時間から夜になりますから、光を楽しむにはうってつけなのです。
駅前やショッピング施設のイルミネーションがとてもきれいです。
このイルミネーションを自分で作って楽しむことができます。

LEDライトの開発によりわたしたちが自分でイルミネーションを作って楽しむのが簡単になりました。
LEDは熱くならない電球ですから、植物に巻いても熱で傷つけることはありません。
庭の植物にこのライトを巻くだけできれいな装飾を作ることができます。
植え込みがある家ではこうした演出をすることができます。
こうした明かりがあることで、わたしたちのみならず近所の方々の心を照らします。
地面にもライトを並べて光の通路を作ったり、地上絵を作ったりすることができます。
ライトを傷つけず、泥だらけにもせずに作る方法があります。
その方法が人工芝です。
人工芝はポリエチレンといった化学繊維から作られるのですが、熱に弱いという欠点があります。
LEDライトは熱を発しない明かりですから、人工芝の上に置くことができます。
人工芝のクッション効果でライトを傷つけることはありません。
掃除もしやすくいつでもきれいな人工芝で光の演出をすることができます。

この人工芝の素材はピンからキリまであるので、クッション性に大きく影響を及ぼします。
そのため安いものを買ってしまうと芝葉が硬くてライトを傷つけてしまう恐れがあります。
せっかく導入するのですから後悔しないものを選びたいものです。
冬は長いですから少しでも楽しめるものは増やしたいものですね。
ベランダで簡単人工芝ライフ

「うちはマンションだし、人工芝なんて縁がない」と思っているみなさん!
大いに関係あります。
マンションにはベランダがあります。
オープンバルコニーのような立派なものから一般的な洗濯物を干すだけの場所まであります。
一般的な狭いベランダでも人工芝を敷くメリットがあります。
ベランダはコンクリート舗装がされていますが、この上に人工芝を敷くとコンクリートの劣化を防ぐことができます。
今までの生活でついた汚れを目立ちにくくする効果があります。
見た目が鮮やかできれいです。
裸足でのっても痛くないですから、ベランダサンダル要らずです。
クッション性が高いので、子供のちょっとした遊び場として利用できます。
大人にとっては椅子を置けばくつろぎの場所へ変身することができます。
公園で本を読むようなゆったりとした時間を家のベランダで行うことができます。

ベランダは庭と違って草むしりも土づくりも必要ありません。
防草シートも敷く必要はありません。
そのため、比較的簡単に設置することができます。
ベランダに敷く場合前にゴミをしっかり取り除くようにしてください。
ベランダの場合は釘が打てませんので、両面テープを使用します。
専用のテープを買って使うようにしてください。

どうしてもベランダに人工芝を敷くと「水はけ大丈夫?」と気にされるかと思います。
芝人の人工芝は葉の部分の表面積が多いため、「表面排水」で自然に排水していきます。
また、裏面に排水穴があいていますので、こちらからも水が流れていきます。
しかし、安い人工芝を買ってしまうと水はけの悪い製品があります。
そうすると、いつまでもジメジメした環境が続くため、カビや細菌が大量繁殖します。
ゴキブリは湿気を好む虫で湿度75%~100%で大量繁殖します。
残念ながらゴキブリは冬眠しません。冬でも油断大敵です。
一方で水はけがいいからと、すのこのような人工芝を買ってしまうと、足の裏が完全にチクチクします。
ベランダとはいえ外に置きますから、紫外線で劣化しないものを選ぶ必要があります。
防草シートを考える

普段マンションで生活をしているとお世話になることはほぼないのですが、庭付き一戸建となると庭の管理も含めてやることが満載です。
草取りをするときに除草剤を使うか?使わないか?という問題があります。
まだ庭のある家に住んでいたころは除草剤を使ったり、火で燃やしたりして草の処理をしていました。
腰が痛くなるので、立ったままでできる鍬のようなものを使うこともありました。
除草剤を使わない方法として「防草シート」があります。
今回はこの防草シートについて解説します。

防草シートは日光を遮ることで草の光合成を止めて生長させないことを目的に使用します。
また覆うだけでいいという簡単さからどなたでも使用できます。
この防草シートはホームセンターで誰でも買うことができます。
素材は化学繊維であるポリプロピレンやポリエステルを使ったものが多いです。
厚手のものと薄手のものがあります。
葉先がとがっているような植物が多い時は薄い素材ですと刺さって破れてしまいますので、厚手のものを選ぶようにします。
また防草シートの上に乗った草の種が発芽して根がシートを貫通してしまっては全く意味がなくなってしまいます。
耐久性を持たせる加工もそうですし、日光を浴びても劣化しない加工も必要です。
せっかく張ったのに数年でボロボロ穴が開いてしまっては意味がありません。
雨が降っても大丈夫なように水はけも必要です。それでいてカットのしやすさも必要です。
庭の形に応じてシートをカットしなくてはならないからです。
何を使ったらいいかわからない時は「ホームセンターで一番高いものを買う」ので間違いありません。

防草シートは覆うだけでいいのですが、光が少しでも入ってしまうと草が生えてきます。
決して隙を与えてはいけません。
そのため、シート同士を重ね合わせて、重なったところを固定します。
シートを張って完成というのもいいのですが、その上に人工芝を張ると土地の有効活用ができます。
景観美しく、遊んでも寝てもよしです。
この人工芝においても耐久性を考えて買うようにしてください。
庭の手入れ時短術
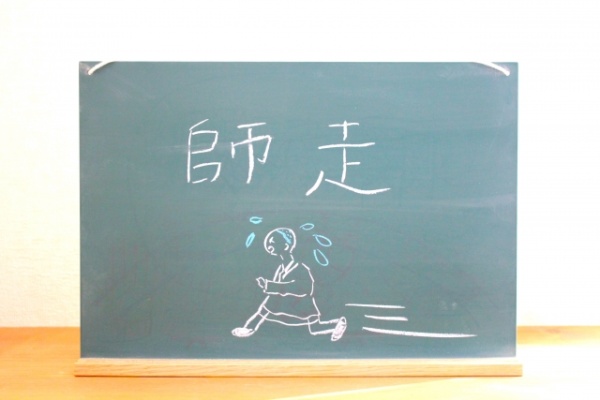
いよいよ今年も残り1か月ほどとなりました。
12月になるといよいよ冬到来ですね。
今シーズンのウインタースポーツを始める方が出てきました。
こうした季節ものはその時でしかできないため、いつ誰とどこへ行くのか?計画的に行いたいものです。
そうでなくても年末が近づいてくるため「大掃除」というものがやってきます。
もちろんやらなくても変わらないのでは?という意見があることでしょう。
年に1回大掃除をすることで「年神様」をしっかりお迎えすることができると言われています。
同じ年の始まりならスッキリとした状態の方が気持ちいいものです。
家の中至るところの掃除もありますが、まずは庭をきれいにしていきましょう。
年末に掃除をすると気温が下がっていますので、外にいるととにかく寒いのです。
そのため大掃除のうち外の部分は早めに終わらせておくようにしたいものです。

ちょうど落ち葉が多い時期でもございますから、落ち葉の掃除をすることが先決です。
自宅に樹木を育てていなくても、風にのって自宅の敷地内に入ってきてしまいます。
冬は一年生草本が枯れていますので、草取りの負担が最も少なくなります。
そこで多年生草本を根こそぎ取りするにはこの季節が最も適しています。
ここを逃すとまた来年に草がボーボー生えてしまいます。
庭のお手入れで最も大変な作業が草取りです。
だからこそ、ここをやっつけてしまえばあとは楽々なのです。
この草が10年生えない環境を作れるとしたら?
すごくないですか?
人工芝を施工する過程で必ずやることが草取りと下地作りなのです。
これをすることで、10年間草が生えない土壌を作ることができます。
丁寧な下地作りの上に人工芝を敷きます。
こうすることでお手入れが簡単に生まれかわります。

人工芝のお手入れはほうきや掃除機を使い、ゴミを除去することと、ブラシで芝葉を起こすことの2点です。
そのため短時間でお手入れを終わらせることができます。
まだ人工芝を導入していない方は今のうちに始めておくと後が楽になります。
冬でも人工芝

都市部ではちょうど紅葉の見ごろです。
そうは言っても街路樹のイチョウが黄色になっているとか、
公園の桜の木が紅くなっているとかその程度ですが。
そして落ち葉の季節です。
公園の管理人さんたちが毎日竹ぼうきで落ち葉を集めています。
いよいよ冬がやってきます。
冬でも人工芝で楽しむことができます。
まずは緑が欲しい時、緑に癒されたい時です。
一年中色鮮やかな緑でわたしたちを待っています。
一年を通して青々とした緑の庭や屋上が欲しいという時は
人工芝を使えば簡単に叶えることができます。
一方で季節感に合わせて緑では違和感があるという方もいらっしゃるでしょう。
緑色以外のカラー人工芝で、季節感に左右されないデザイン性のあるお庭を
楽しむこともできます。

天然芝は枯れてしまいクッション性を失いますが、
人工芝を使えばいつでもふかふかな状態で楽しむことができます。
小さな子供でも安全に遊ぶことができますね。
掃除やメンテナンスの点においても人工芝を使えば楽々に終わることができます。
冬になり雪がうっすら積もることがあるでしょう。
こういう薄い積雪では泥と混ざって歩くときにぐちゃぐちゃになるのですが、
人工芝を使えば土の部分と雪の部分に人工芝という仕切りができますから、
雪の上を歩いても汚れることはありません。
除雪作業においては、ほうきやスコップで雪を掃けば大丈夫です。
泥で汚い雪ではないですから、除雪作業においても気分よくできます。

雪で芝葉が寝てしまうので、そういう時はブラシでしっかり葉を起こすようにしてください。
芝葉が寝ているとクッション性が悪くなりますし、劣化も早まります。
一年中楽しく過ごせる人工芝です。
「こどもは風の子」ではないのですが、外で元気に遊ぶ子供たちの姿はいいものです。
雪のある地域では雪が降る前に施工をしておくようにしてください。
また、それ以外の地域においては冬にやると下地作りがスムーズに進みます。
一年生草本はほとんど枯れてなくなっていますので、草取りの作業負担が減ります。
そのため、人工芝を導入するなら今がチャンスと言えるでしょう。
公園に学ぶ

わたしたちが普段お世話になっているのが公園です。
子供たちにとっては大切な遊び場です。
ここでたくさん遊ぶことで人間関係はもちろん
自然環境について学ぶことができます。
大人たちにとっても憩いの場です。
ベンチで座って読書をしたり、楽しく遊ぶ子供たちを見たり、
散歩をしたり・・・公園がわたしたちの生活の一部となっています。
この公園の起源ですが、王や領主が所有していた庭を
一般の市民に開放したのが始まりとされています。
日本においても大名庭園がありこれを一般の人に開放していました。
徳川家の庭であった後楽園、偕楽園などが有名です。
そんな公園ですが、先日お世話になったところは小高い丘があり
そこから大きな滑り台がありました。
滑り台の周辺にはクッション性を高めるために人工芝がありました。
広場の方は天然芝がありました。
11月ですので、すっかり枯れ葉色になっていました。
また幼児用の遊び場には人工芝がありました。
11月にもなると天然芝の色が完全に変わってしまい、
人工芝の色と明らかに違うのがわかります。
色の違いに違和感がある方もいるでしょうが、
一年中きれいな緑をしているというのもそれはそれでありなのではないかと思います。
天然芝は冬に向けて枯れてしまうという欠点があるのですが、
人工芝は枯れません。

【芝人大阪府FC 芝の匠】施工
一年中貴重なクッション源として子供たちを守ることができています。
幼児用スペースや滑り台といったクッションが必要なところには
人工芝を使うというのは理にかなっています。
わたしたちの庭においてもクッションが必要な時は
人工芝という選択をするとよいです。
芝葉が濃密に作られているとやわらかくクッション性を
上げることができます。
芝葉の下の素材にクッションを入れるとさらによくなります。
サンプルを取り寄せてクッション性を確認しておくことをお勧めしています。
日陰でも使えるのが人工芝のメリットです。
みなさんの庭の配置に応じて設計することができます。
ゴルフの練習が家でできます

みなさん、ゴルフをやりますか?
かつては「接待ゴルフ」というのが各地で行われていました。
「バブル」の時代にはほとんどと言っていいほど接待ゴルフでした。
職場の人間関係、取引先との人間関係をスムーズに行う手段としてこのゴルフがありました。
日頃オフィスにこもっていると、屋外でスポーツをすると気持ちがいいものです。
特にゴルフ場は郊外にありますから、都会の雑踏を離れることができます。
ちょっとした小旅行感を味わうことができるため、人間関係を良好にする手段としてゴルフは有用です。
しかし、バブルの時代と違って会社にお金がたくさんあるわけではないですから、
接待ゴルフを行う余裕がなくなってきました。
そうはいってもゴルフの魅力が下がっているわけではありません。
このゴルフですが、基本的に一年中行うことができます。
春は気温が暖かく、芝も青々としてきます。
夏は芝にとってぐんぐん伸びる季節です。
強い芝葉がショットに影響を及ぼします。
夏の屋外ですから、暑さ対策が必要です。
秋はベストシーズンと言われています。
空気が乾いてきていますので、屋外での汗がさわやかなのです。
ゴルフの予約においても秋は高く設定されています。
冬は芝が枯れていますので、ショットが打ちやすいです。

【芝人大阪府FC S.N.Yターフ(有限会社 さのや)】
人工芝を使えば家にゴルフ練習場を作ることができます。
秋のベストシーズンに家でゴルフができるのです。
ちょっとしたパターコースを人工芝で作れます。
ゴルフはゴルフの芝が必要です。
プレーに影響が出ないように柔らかい芝葉が必要です。
転がりやすくするため、芝葉の長さを短くしてあります。
こうしたゴルフ専用の人工芝が発売されているので、それを買うようにしてください。
カップの部分に穴をあけてホールカップを取り付ければ完成します。
もちろん天然芝で練習場を作ることができますが、
ゴルフの場合はさらにメンテナンスが必要となります。
芝葉が短いため、芝刈りの頻度を上げる必要があるのです。
しかも生長点を切らずに芝を刈る技術も必要です。
人工芝を使えばこうしたメンテナンスから解放されますので、プレーに集中することができます。
落ち葉で遊んであとは掃除

そろそろ住宅地でも至るところで紅葉に落ち葉とすっかり晩秋を感じるようになりました。
落ち葉は掃除が面倒なのですが、子供にとって落ち葉は立派な遊び道具です。
「子供は風の子」ですから、外でたくさん落ち葉と触れ合っていくのもいいですね。
外に出ると日本の四季を感じることができます。
子供はこの四季を覚えている段階ですので、
「秋になると葉っぱが落ちてくるよ」と教えてあげるとどんどん興味が出てきます。
イチョウの葉を使って引っ張り相撲をやると楽しいですよ。
どの葉っぱが一番強いでしょう?
また、落ち葉プールを作ってモフモフするのも楽しいです。
モフモフしたところにジャンプするのが面白いです。
きれいな落ち葉を使ってしおりを作るのもいいですね。
しかし、家の庭に落ち葉があるとどうしても「掃除」のことで頭がいっぱいです。
人工芝を敷いている家庭において落ち葉は大敵です。
人工芝の見た目が悪くなるだけではありません。
落ち葉が乾燥し粉々になり人工芝の中に入り込みやすくなったり、
落ち葉の下がじめじめとし、虫や、コケ等発生しやすくなることがあります。
そのため、速やかに掃除を行うようにしてください。

大量の落ち葉はほうきを使って掃き掃除をします。
ほうきの素材はナイロンを使った方が芝葉に優しいです。
芝葉の奥に絡んでしまった落ち葉はほうきでは取り除きにくいですので、
掃除機を使って吸っていきます。
「ブロア」といって風を出す機械があります。
これを使うと強い風で吹き飛ばしてくれます。
集めた落ち葉は家庭ごみとして捨てるか腐葉土として再利用するかします。
ごみに出す方が簡単ですぐに終わるというメリットがあります。
再利用するとごみを減らすことができます。
腐葉土を作ることができればわざわざ買いに行かなくていいのです。
子供と一緒に作ってみると学習になります。
落ち葉などのゴミを取り除いた後は、芝葉をブラッシングしていきます。
寝ている芝葉を立たせるようにブラシをかけます。
こうすることでより長持ちさせることができます。
人工芝を導入するのはいつがいい?

一年中きれいな人工芝なので、思い立ったらすぐ導入を決めることができます。
そのうちいつやるとスムーズに進むか?ということを考えていこうと思います。

春は気候が穏やかで温かいです。新しい命が芽生えすくすくと成長していきます。
どんどん草が生え始めてくるので、除草の負担がかかります。
人工芝を導入してすぐ使えるというのは春ならではです。外で遊ぶのにいい時期です。
新品のふかふか人工芝でカフェを楽しんだり、飛んだり跳ねたりして楽しむことができます。

夏は最も草が生えてくる季節です。
「自分で草取りするのがもう無理だ!」とギブアップしてしまいます。
そこで人工芝を導入します。
除草の負担が最もかかりますが、ここを乗り切れば草のない世界が待っています。
新品の人工芝で夏遊びがすぐできます。ビニールプールをのせてもいいですね。
プール利用時は裸足になりますから、裸足でも汚れない痛くない人工芝は最適です。

秋は気温が下がり涼しくなります。
少しずつ草が枯れてきますので、草取りの負担が下がってきます。
そのためスムーズに人工芝を導入することができます。
外での作業がしやすいのでここで始めるというのも一つの手です。

冬は草がほとんどなく草取りが早く終わります。
そのため下地作りがスムーズに進みます。
外での作業は寒いですが、下地作りが早く終わるのがいいです。
下地作りが人工芝をきれいに張るためのポイントとなりますから、ここの作業負担が少ないのはありがたいです。

まとめると、春夏は敷いたばかりの人工芝をすぐ活用できる、秋冬は下地作りの負担が少ないということです。
梅雨の時期は雨が降って地面が安定しないので、ここは外した方がよいと考えられます。
いつやるにせよ、やると決めた時が自分たちのベストシーズンなのです。
人工芝を導入する目的は何なのか?
草のない世界?
裸足で遊べる場所?
くつろぎの場所?
駐車場として?
こうしたことを踏まえて計画的に進めていきたいものです。
不安なことがあれば芝人スタッフまでご相談ください。
観光地は混んでいます

例のウイルスが鎮静化しつつあるので、週末に出かけてみました。
なんと!車は大渋滞でした。
考えることは一緒なのですね。
中央道は八王子あたりから止まってしまいました。
「中央道のオアシス」こと談合坂SAでは家族連れがたくさんいました。
山梨県の名産品に舌鼓を打ちつつ目的地へ向けて英気を養っていました。
場所を選ばないと混んでいるところに当たってしまいます。
車は便利ですが、渋滞にはまってしまうと何もできません。
だからこそ、家に遊べる場所があるというのはとても大切なことです。
渋滞の影響なく、いつでも遊べるのです。
出かけることで解放感や空気感を含めて楽しむことができます。
そこを何とかその環境に近づけるようにします。
ただの砂利、ただの庭といったところをリフォームするのです。
砂利は清潔感がありますし、安く導入することができます。
しかし、そこで遊ぶことはできません。
転んでけがをするからです。
ただの庭においてもとりあえず歩くことはできますが、遊ぶことはできません。
ここを人工芝にリフォームすることで遊び場を作ることができます。

現在発売されている「リアル人工芝」は天然芝と同じ見た目をしています。
クッション性に優れており、その上で走ったりしても足腰を痛めることはありません。
しなやかな芝葉は転んでも大きなけがはしにくくなります。
人工芝においては品質に差が大きいため、クッション性やしなやかさは実物を手に取ってみないとわからないことが多いです。
ネットの写真だけで選ぶということがないようにしてください。
ホームセンターに行けるようならば、行って実物を触ってみるようにしてください。
ネットの場合はサンプルの取り寄せができるところを選ぶようにしてください。
実際に触ってみると「こんなはずじゃなかった」ということが回避できます。
見た目はもちろんクッション性、芝葉の柔らかさも含めて確認するようにしてください。
家で遊べる場所を作るために人工芝という選択肢は有用です。
観光地が混んでいても家でできることはあります。
ブタクサが猛威を振るっています

こんにちは。道路の路肩はもちろん、空き地や公園でブタクサが猛威を振るっています。
みなさん、このブタクサってどんな植物かご存知でしょうか?
ブタクサはキク科ブタクサ属の一年生草本です。背丈は人間の身長ほどあります。
黄色い花を咲かせます。
この花は風媒花であり、風に乗って花粉を飛ばします。
また、「何にもならない植物」として知られています。
この花を観賞しても心が癒されるわけでもないですし、花からはアレルゲンとなる花粉を飛ばします。
ヨモギのように食べられるわけでもないです。
その上、他の植物の生育を抑える作用があります。
きれいな花を育てようとしても、ここにブタクサがあったらすべて水の泡です。
ブタクサ畑になってしまいます。
繫殖力が高いため、1年に2回草取りをしただけでは、草取りをしないのと同じ被害が出てしまいます。
そのため、1年に3回以上草取りをする必要があります。
ちょっとドライブをして窓を開けようものならブタクサ花粉が大量に入ってきます。
その辺の散歩をしようものなら人間の顔の位置に花があるため、超近距離で花粉を吸いこんでしまいます。
だからこそ、せめて自分の庭だけはブタクサの被害をなくしたいものです。
この草対策に人工芝を導入するという方法があります。

人工芝を敷く過程において必ず「完全な草取り」があります。
その上に防草シートを張ります。
こうすることで太陽の光が土に届かなくすることができます。
光がわずかでもあれば、光合成ができてしまうので植物は生長してしまいます。
もちろん防草シートで終わらせてもいいのですが、人工芝を敷くことで見た目と機能において楽しめるのです。
リアルな芝を再現しているため、ふかふかで気持ちがいいのです。
この上で遊んだり寝たり、自由自在に楽しむことができます。
見た目もリアルな芝と同じですから、いつでもきれいな状態を維持することができます。
メンテナンスのやり方は基本的にはごみ取りとブラッシングです。
芝葉をブラッシングによって立たせることができます。これによりいつまでもふかふかの人工芝を維持することができます。
ブタクサの被害から回避するとともに、楽しい場所を作ってしまうという人工芝です。
積極的に導入したいものです。
「こんなはずじゃなかった」とならないために
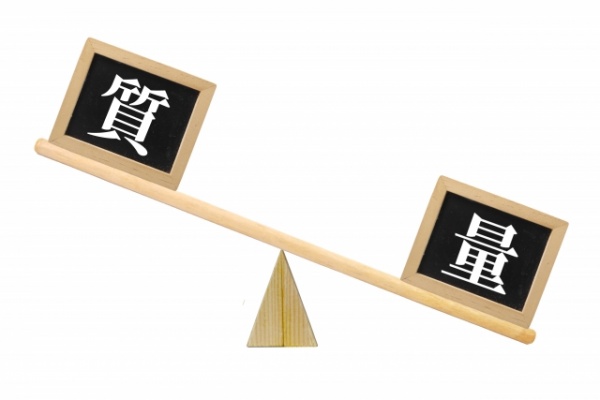
今までの買い物で「こんなはずじゃなかった」ことは一度や二度ならずあることでしょう。
実は散髪代を抑えようとバリカンを買ったのですが、1880円の安い商品を買ったところ半年で動かなくなってしまいました。
硬い髪の毛を毎回切っていたことからモーターが止まってしまいました。
その後4980円の商品を買ったところ快適に散髪をすることができています。
美容室に行く値段よりは安いのですが、それでも初めから品質重視にて買っていればよかったわけですから「こんなはずじゃなかった」のです。
また、自分を変えようとセミナーに出かけたところ、
何十万もする定期コースを申し込ませるための説明会に過ぎなかったことがあります。「こんなはずじゃなかった」のです。
だからこそもう一度立ち止まって考えてほしいのです。
人工芝のある庭に憧れていても、今みなさんが考えている方法ではうまくいかずに回り道をしてしまうことだってあるのです。
安いバリカンを買って結局高いバリカンを買い直すくらいなら、初めから高いバリカンを買った方が得なのです。

【栃木県FC加盟店 芝笑(インプルーヴ那須合同会社)下地施工】
人工芝のある庭を成功させるポイントは土づくりなのです。
土がデコボコならば人工芝はデコボコになります。
土がふにゃふにゃならばピンが刺さらないため、人工芝はずれずれになります。
水はけが悪い土はカビや虫が発生します。
人工芝を敷いても、水はけは改善されることはありません。
そもそも草むしりが完全ではないと、人工芝を敷いても完全に雑草除去されず、後に下地の不具合や雑草が生えてくることもあります。
この土づくりを完璧に行っておく必要があります。
ここを疎かにすると「こんなはずじゃなかった」ということが起こってしまいます。
芝人は過去の「こんなはずじゃなかった」事例を救済してきた実績が多数あります。
それは人工芝を敷くための土づくりからたずさわっているからです。
その上で高品質の人工芝を敷きます。
高品質の人工芝を使うと紫外線による劣化を抑えて10年間もたせることができます。
「こんなはずじゃなかった」と後悔する前に、芝人スタッフに相談してみてはいかがでしょうか?
バーベキューをお手軽に

先日、埼玉県にある「キャラバンパーク所沢」が「モヤモヤさまぁ~ず2」というテレビ番組で紹介されていました。
バイパス沿いすぐの立地でキャンプ気分を味わうことができる施設です。
本格的なキャンプ場へ行くのは遠いですし、難しそうというハードルがあります。
そこで、こうした施設を利用することでキャンプとはこういうものだよというのを体験することができます。
薪割りもスタッフさんが教えてくれるので、簡単にすることができます。
焚火セットと網を購入すればバーベキュースペースで調理をすることができます。
アウトドア用の椅子がレンタルできますので、椅子に座ってゆっくり食べることができます。
火は古代よりわたしたしの生活にとって切っても切り離せない存在です。
暗い夜を明るく灯してくれます。
温かい料理を食べることができます。
寒さをしのいでくれます。
それとともに火を見ていて飽きないというか、むしろずっと見てしまうものです。
規則性のない空間的・時間的な変化を与えてくれます。
これを「ゆらぎ現象」というそうです。
このゆらぎは脳内でα波を発生させてリラックス状態を作ります。
都市型生活をしていると残念ながら焚火をする機会はありません。
キャラバンパーク所沢ではバーベキュースペースに人工芝が敷いてあります。
こうすることで幹線道路沿いにもかかわらず緑の演出をすることができます。
緑の地面があってバーベキューコンロがあってその周りに椅子が並んでいるといい画が撮れます。
人工芝の素材はポリエチレンやポリプロピレンといった化学繊維ですので、熱さ対策をしないと溶けてしまいます。
その分、こうした施設では高さのあるバーベキューコンロを使用しているため安全に使用することができます。

これを見ていると自分の庭でできないかな?と思うわけです。
実際できます。
庭に人工芝を敷いて、高さのあるバーベキューコンロを買う。
アウトドア用椅子を買う。
あとは食材を買って実行に移すのみ!人工芝の敷き方がわからない方は芝人スタッフまでお問合せください。
テレワークなどで家も仕事場になってしまっているとどうしても気持ちの切り替えがうまくいかないものです。
あえてバーベキューをやって脳内α波を出してみるのはいかがでしょうか?
※人工芝は、火の粉にても溶ける恐れがございますのでご注意くださいませ。
スポーツの秋

スポーツの秋ですね。
各地で運動会をやっているところが多いようです。
この時期は気候も良くてスポーツがしやすいです。
先代の東京オリンピックが行われたのが1964年ですね。
この開会式が10月10日に行われたことからその後「体育の日」として制定されました。
なお、今年は東京オリンピックが夏に行われたため、開会式の日に祝日が移されたのでした。
学校の運動会では土のグラウンドで行うことが多いですね。
前日に雨が大量に降ってしまうとグラウンドコンディションが悪くなってしまうので、
当日がきれいに晴れていても運動会が開催されないということが多々ありました。
昔は裸足で行う競技もあり、小さい石が足に刺さって痛かった思い出があります。
高校に入学してからは、校庭がウレタンに変わりました。
ウレタン舗装は適度な弾力性があるため、衝撃を吸収することができます。
そのため安全で快適に運動をすることができます。
当時の校庭が狭く、運動会をやるにはオーディエンスが入らないため当日は広い天然芝のグラウンドを借りて行っていました。
このグラウンドは天然芝が広がっていて、応援席にレジャーシートを敷いても痛くありませんでした。
騎馬戦で転んでも擦り傷はできず快適に過ごすことができたことを思い出します。
安全に運動ができるのが分かっていますから、思い切って実力を発揮することができます。

(イメージ画)
しかし、天然芝のグラウンドでは虫がレジャーシートに上陸してきます。
それを追い払うのが大変でした。虫嫌いの子も多いですから、虫対策は必須です。
現在は人工芝の品質が向上したことで、人工芝のグラウンドを採用する施設が増えてきました。
虫が発生しませんので虫嫌いの子がいても大丈夫です。
クッション性に優れていますので天然芝の様な安全性で運動をすることができます。
水はけがいいため、土のグラウンドのようにぐちゃぐちゃになることはありません。
水が引くのを待たなくてもすぐ使うことができます。
もちろん人工芝によっては裸足でのると痛いものがあります。
実際にサンプルを取り寄せてクッション性、安全性を確認しておくことをお勧めしています。
食欲の秋はBBQ

BBQといえば夏のイメージが強いですが、秋のキャンプシーズンこそバーベキューの本領を発揮します。
何しろ「実りの秋」であり食材が豊富にあります。
おいしい食材ですから焼くだけ、煮るだけといったシンプルな調理方法で素材の味を引き立たせることができるのです。
おいしいきのこが採れるのはまさに秋ならではです。
実際きのこは一年中生えているのですが、気温と湿度の影響を受けていますので梅雨と秋雨のある時期に大量発生することができます。
また、きのこ王である「松茸」は日本の気候において秋にしか生えません。
また秋にはイモ類が収穫できます。
レンチンのイモより焼き芋がおいしいのは当然のことです。
でんぷんを糖に変換するβアミラーゼという酵素があります。
この酵素が最も活性化されるのが70℃です。
ここを長い間維持できると糖が増えるので、甘くておいしい焼き芋ができるのです。
電子レンジを使うとこの時間が短くなってしまうため、おいしく感じないのです。
さんまや鮭は秋に収穫すると脂がのっていておいしいです。
焼く調理が最も適した食材です。

夏のバーベキューは火が熱いのですが、秋は火で暖を取れるためちょうどいいのです。
涼しくなるほど虫が減ってきますので、外にいても快適なのです。
緊急事態が終わりましたからキャンプ場へ行くことができますね。
手軽に屋上でバーベキューができる施設もあります。
もちろん家でやってもいいですね。
家庭に人工芝がある場合は注意事項を守りさえすれば楽しくBBQできます。
何といってもふかふかできれいな人工芝は気持ちがいいです。
快適に食事を楽しむことができます。
注意事項ですが、防火シートを敷いて熱源の影響を抑えるようにしましょう。
人工芝は化学繊維でできていますので、燃えると大変なことになります。
油が付いたところは中性洗剤でこすって汚れを落としておくようにします。
食べくずは掃除機で吸い取ります。
きれいで済んだ空と美しい人工芝においしい食事でこの秋を満喫してはいかがでしょうか?
デザインが自由自在

「芸術の秋」です。
秋には大きな美術展が続々と開催されています。
通常の展示の他に期間限定で見ることができる特別展示もあります。
日本に居ながらにして世界の大作を見るチャンスがあります。
夏の暑さが和らぎ肉体的にゆとりが出てくるからこそこうした芸術をじっくり感じ取ることができるのです。
作品を作る上でも気温がちょうどいい時期は繊細な表現ができるようになります。
日本の秋は景色が美しいです。
その情景も含め美しさを引き立たせます。
屋外展示である「箱根彫刻の森美術館」は日本の美しい景色を含めて鑑賞します。
見上げれば紅葉があり、地面には美しい天然芝がありその上に彫刻が展示されています。
秋だからこそこういう美しさがあります。
芸術の秋ですが、わたしたちの庭で作ることができます。
人工芝を使うとそれが可能です。
人工芝には緑の他にグレーとブラウンがあります。
この3色を組み合わせるとわたしたちの庭で大きな作品を作ることができます。
水玉模様にストライプ、市松模様・・・3色ありますので、より表現が豊かになります。
もちろん、くまさんやうさぎさんを作ることだってできます。

こうした模様を作ることができるのは職人さんのカット技術があってこそなのです。
大きな庭のデザインを考えつつ隙間なく組み合わせていかなくてはなりません。
そしてカットした芝を切れ目なく隙間なく合わせる技術が必要です。
模様を作ってもそこに隙間ができてしまっては見た目が悪く、つまずいてしまうからです。
芝がめくれてしまうとケガにつながりますので、丁寧に繋ぎ合わせる技術があります。
複数の芝を組み合わせますから、芝葉の向きも考えて作ります。
グレーの芝は右向きで、緑の芝は左向きですと見た目が悪くなりますし、触感も悪くなります。
芝人の職人さんはプロの競技場をはじめ、様々な場所で施工した実績がありますのでどんなデザインにも対応することができます。
人工芝の作品、澄んだ青空、美しい紅葉とあれば心が豊かになりますね。