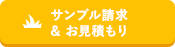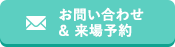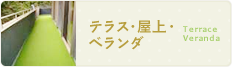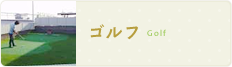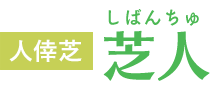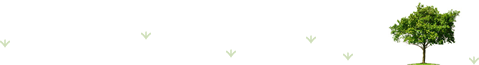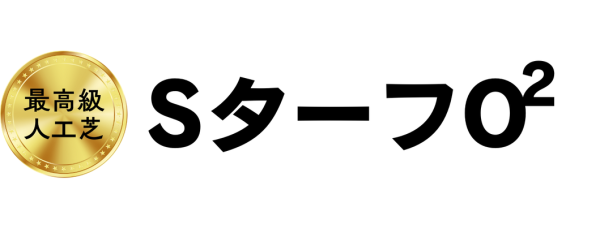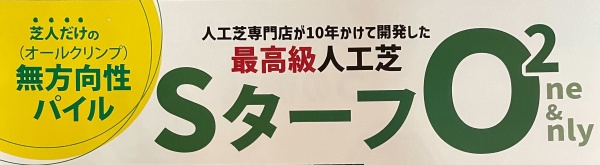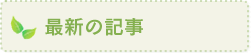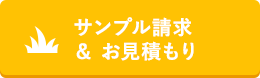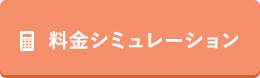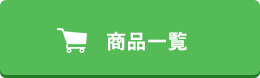相手を気遣うために人工芝がある
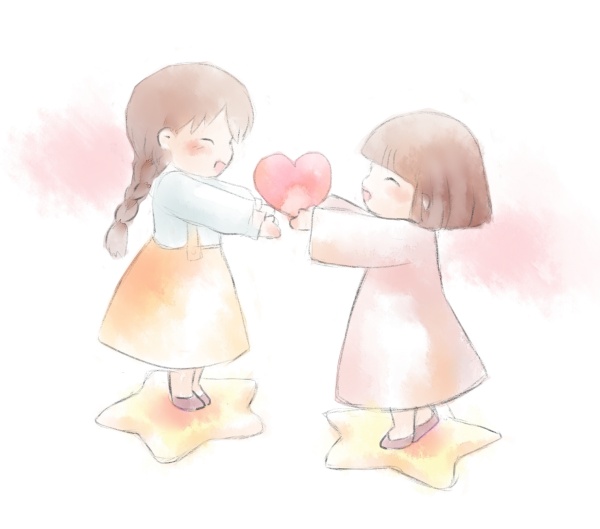
普段、わたしたちは相手を気遣って生きています。
相手を気遣うことは人間関係を円滑にする上でとても大切なことです。
相手の立場や気持ちを考えて、
思いやりのある言葉をかけたり行動に移したりします。
また、相手が困っていそうなときには
さりげなく声をかけることで信頼関係を深めることができます。
人工芝を敷くことが「相手を気遣う」行動の一つになっています。
泥や虫の心配がなく清潔な状態で利用できるからです。
「子供は泥んこになって遊ぶのがいい」というのは一昔のことです。
体を動かす遊びは必要ですが、
泥んこになると「衛生面」という観点からは推奨できないというのが現在の考え方となります。
もちろん予防接種で予防できる病気はあるにせよ、
傷口に泥がついている状態では感染リスクが高まります。
虫刺されのリスクについても考えておく必要があります。
蚊は血を吸って回ることから、
無差別的に「注射針の使い回し」をしている状態となります。
誰かの血液がついた針を自分の血管に入れられている状態です。
これは本当に恐ろしいことです。
蚊を媒体とする病気がある以上、
虫の心配がなく遊べることが「相手への気遣い」でもあるのです。
蚊以外の虫についても、一昔では考えられなかった外来種が入ってきています。
それについては今までの常識が通用しません。

泥ハネについては汚れた洗濯物を洗う大人たちを悩ませます。
買ったばかりの洋服に限って泥で汚れてしまうものです。
子供服なので汚れるのは当然のことかもしれませんが、
せっかく買ったものですから、長く大切に着てほしいと思いますよね。
泥汚れは単に洗濯機に入れて洗うだけではなかなか取れません。
泥というのは不溶性の粒子だからです。
それが繊維の奥まで挟まってしまい取れていない状態なのです。
泥汚れは繊維の奥に行く前に、叩き落とします。
その後、「ウタマロ石鹼」のような固形石鹸を使ってこすります。
石鹸の力で汚れを浮かせるのです。
そして漂白剤を上からかけます。
その後、通常の洗濯物と一緒に洗います。
人工芝を敷くことで泥汚れの心配がなく過ごすことができます。
つまり、ひと手間以上かかる泥汚れ対策から解放されるのです。
これは洗濯をする大人たちを気遣うことになるのです。
雑草についても大人たちを悩ませます。
雑草はわたしたちが意図するように生えてくれません。
だから「雑」草なのです。
雑に生えてくれるので、見た目が悪くなります。
雑に生えてくれるので、つまずきなどのケガをしやすくなります。
勝手に生えてくるので、意図して生えていてほしい植物の居場所を奪います。
だから、雑草は抜かなくてはなりません。
この手間というのはとてつもない重労働となります。
根からしっかり抜かないとまた生えてくるからです。
人工芝を敷くことで雑草から解放されます。
人工芝を敷く過程において「防草シート」を敷きます。
このシートは遮光性の高いシートのことで、
雑草が光合成をするのを遮断することができます。
栄養分が作れない植物は枯れていきます。
防草シートを守る目的で人工芝を上から敷くことになります。
人工芝は、草で悩まされている大人たちを気遣うことになります。
このように、人工芝というのは相手を気遣うツールでもあるのです。
変わらないものに価値がある

あんなことやこんなことがあったのにまだたったの一年だった!
という気がするほど、
ここ数年は時代が目まぐるしく変わっていくのを感じます。
流行や技術は次々と移り変わっています。
ロボット掃除機の先駆者である「ルンバ」ですら、
昨年倒産してしまったのです。
どれだけすごいものでも、「変わらずに、存在し続ける」ことが
難しい時代となっているのです。
その中で「変わらずに、存在し続ける」ものは、
わたしたち人間の心の支えになりますし、
安心感を与えますし、そこが帰る場所になったりするのです。
・ずっと同じ味の料理
・変わらない家族の習慣
・何年たっても変わらない友情
・自分の中の信念や美意識
これらのものは変わらないからこそ、
「信頼」や「安心」を生んで、価値が積み重なっていくのです。
たまに帰りたくなる「マクドナルド」ですが、
ここに帰るといつものメニューが待っていてくれます。
もちろんオペレーションはずいぶん変わったのですが、
期待を裏切らないメニューが待っていてくれます。
自分の中では「ビッグマック」こそマクドナルドだと思っていて、
そのために帰るわけです。
ビッグマックを超えるメニューはあるのか?
と常日頃思って様々なメニューを食べるものの、
結局そこに帰ってくるのです。

わたしたちの仕事である「人工芝」ですが、
これも長い間続けてきたからこそ
「変わらずに、存在し続ける」ものとなってきています。
人工芝自体も「変わらずに、存在し続ける」ように改良を重ねて今があります。
すぐに経年劣化をしてはその価値がなくなるからです。
長い間使用し続けると、色褪せというのが特に目立ってきます。
色素を作る化学物質があるのですが、
紫外線によってその化学構造が破壊されてしまうのです。
赤や黄色の色素は破壊されやすいため、色褪せしやすい性質があります。
注意してほしくて赤字にしているにもかかわらず、
長い間掲示していると赤字だけが見えなくなっているということは
経験としてあるのではないでしょうか?
人工芝の場合は緑を作るために黄色の染料を使います。
そのため、長い間敷いていると色褪せが目立ってきてしまうのです。
一度敷いたら「変わらずに、存在し続ける」ために人工芝があります。
だからこそ、色褪せに強い必要があるのです。
芝人の人工芝はサッカー競技場で使用できるものであり、
その厳しいFIFA基準をクリアしたものです。
競技で使うものだからこそ、スライディングなどの摩耗にも強いです。
それを一般家庭に敷くことができるのが芝人の人工芝なのです。
一度敷いたら、「変わらずに、存在し続ける」ことができます。
いつもきれいな景観がわたしたちの帰りを待っていてくれます。

家に帰れば遊ぶ場所がいつもあります。
自分の居場所がいつもそこにあるのです。
それがわたしたちの安心につながります。
花粉症を気にするようになりました

「春の訪れは花粉症から」というのが、すっかり定着してしまいました。
二人に一人が花粉症であるといわれています。
これは都市部においては6割ほどが花粉症にかかっています。
かなりの数字ですね。
都市部においてはビル風が吹いていて花粉が舞い上がりやすい性質があります。
また、花粉が付着しやすい建物がたくさんあります。
そうした背景からも都市部では花粉症にかかる人が多いとされています。
3か月ほど市販薬で「耐える」ことが現在の推奨とされています。
市販薬では比較的安全性が高く効果もそれなりにある薬が多数販売されるようになりました。
これらを使って3か月ほど症状を和らげれば多くの方はそれで終わりになります。
症状がひどい方においては医師の管理下のもと原因治療を開始するのがよいとされています。
原因治療をすることで、あれほどかゆかった目の症状が全くなくなってきています。
また、強い薬を使わなくても症状が落ち着いてきているのです。
花粉症の治療は薬によるものがメインとなるのですが、
花粉そのものを減らすことが花粉対策において大切なことなのです。
もこもこの服よりつるつるの服を着るようにします。
まだ寒いので、もこもこで暖かい洋服を着たくなるのですが、
上着としては不向きです。
キルティングダウンは外側の素材が化学繊維であることが多いのでつるつるしています。
それでいて中に詰めてあるダウン素材は空気をたくさん取り込む性質があるため、
とても暖かく過ごすことができます。
つるつるの上着は玄関前でバサバサと動かすだけで、表面上の花粉が取れます。
これで家の中に持ち込ませる花粉を減らすことができますね。
外の環境に目を向けてみると、花粉のある場所はないですか?
人工芝は名前の通り「人工」で作った「芝」になります。
人工物ですので、花粉を発生させることはありません。
そのため、人工芝のある場所は発生源ではないことから安心して使うことができるのです。
空から降ってきた花粉については重力がありますから、
風のない場所では降り積もります。
積もった場所に掃除機をかけてしまえば吸い取ることができます。
また、水を撒いてしまえば一緒に流されます。
水を撒く方法ならば、花粉を飛散させることなく一掃できてしまいますね。
定期的に除去することで、人工芝に付着する花粉の影響を
ほぼゼロにすることができますので安心ですね。

とはいうものの、花粉症の方は外で作業なんかできない!!
というのが現実的かと思います。
人工芝の上で何かをするという方でない限りは、
最低限ゴミを取るだけでもいいのです。
花粉が飛散している3か月は家の中から人工芝の景観を見て楽しみ、
それが終わってからブラッシングなどの作業をするのが現実的となります。
花粉を吸い込むリスクのある外での水やり、草取り、芝刈りといった作業がないだけでも
人工芝を敷く価値はあります。
室内から眺める人工芝もいいものです。外に出なくても美しい緑を楽しむことができますよ。
人工芝を敷いて大丈夫なの?

【群馬県FC:株式会社SEIGA 施工 】
このブログはもちろんのこと、
他の記事でも取り上げられていることと思いますが、
人工芝は便利です。
自分の生活が3段階くらい豊かになっているのを感じるわけなのですが、
それでも人工芝を敷くことをためらうわけです。
人工芝に限らず人間は初めてのことをやる時は、
不安になりますし、疑問も感じるのです。
今では市民権を得たといっていい「スマートフォン」ですが、
当初は音楽を携帯電話に保存する意味がわからない!
インターネットはパソコンでできるじゃん!
ボタンなくて電話できるか不安・・・という声があったわけです。
マイナ保険証についても今は移行期になるので、
今までの保険証で困っていない!という声が多数あると思います。
これから人口減少が進み、働き手不足というのがありますから、
医療スタッフという限られた資源を「診療すること」に集中させる必要があります。
保険証の資格確認を「人間」が「目視」でやり、
それを「手」で入力するというアナログの方法をいつまでも続けるのは非効率です。
それを少ない働き手でやると、「待ち時間」という形でわたしたちに返ってくることになるでしょう。
そして、実際にその波がきているわけです。

新しいことは疑問もありますし、不安はあります。
話は人工芝に戻すのですが、よくある不安や疑問は次の通りになります。
- うまく敷けるか心配
- 失敗したらどうしよう
- 見た目が不自然にならないか
- メンテナンスや耐久性についての疑問
これらの不安は、情報や準備をしっかり行うことで軽減できます。
芝人スタッフは販売から施工まで一貫して行っているのが強みになります。
わからないことはわたしたち芝人スタッフに相談しましょう。
情報をたくさん持っているのは結局のところプロなのです。
ちなみに、芝人の人工芝を芝人スタッフが敷いた場合は次の通りです。
- プロの技術でうまく敷けます!
- プロの技術があるので、失敗しません!
- 見た目は自然で、つなぎ目はどこでしょう?と探すほどです
- メンテナンス作業は基本的にゴミを取ることと、ブラッシングをすることです。適切にメンテナンスをしてもらえれば10年間使うことが可能です。

失敗しないためにわたしたちは次のポイントを考えながらやっています。
1 事前準備をしっかり行う:
敷く場所はどこでしょうか?寸法を測るというのはもちろんなのですが、
障害物があるのかないのか?というところも確認します。
また、土の質感も大切で、水はけのしやすさということも確認しています。
また、依頼者の要望をよく聞き取り最善な人工芝を選択します。
プロの施工では、道具についてもプロ仕様のものが使えます。
2 設置場所の整地:
人工芝を敷く時に最も大切な作業となります。
水はけが悪い場所においては予め水はけ用の砂を入れる必要があります。
また、デコボコした場所にそのまま敷いてしまうと、
人工芝自体もデコボコしますし、
めくれるリスクや水たまりができるリスクが高まります。
プロならば必要に応じて重機を使って整地することができます。
3 つなぎ目をなくすための技術:
いざ敷いてみると気になるのが、つなぎ目の部分になります。
めくれたり、はがれたりしてくるのもつなぎ目の質が悪いからです。
芝人では人工芝接着剤を使い、丁寧に貼り合わせていきます。
そして釘を打つ場所にもこだわっています。
心配なことや疑問に思ったことは全て解決できるので、
あとは敷くだけとなりますよ。
今年こそは!!

みなさんの中で「今年こそは!」と思っていることはありますか?
ほとんどといって続かないことのひとつに「毎朝のジョギング」があります。
早朝に走っている人を見るとやっぱりカッコいいのです。
しかし、自分がやるとなるとまず早起きしなくてはならないですし、
靴を履いて外出しなくてはならないのです。
その段階を乗り越えてようやく走ることができます。
そこまでしてどうして早朝のジョギングをしなくてはならないのでしょうか?
そこの意味付けが不明確であると続かなくなるのです。
こういう時はマラソン大会に申し込んでしまえばいいのです。
マラソン大会に参加することは決まったものの、
今のままでは確実にケガをするし、本番で絶対苦しくなるし、
そもそも時間制限に引っかかって完走させてくれない!
ということならば、どこかで練習する時間を作ると思います。
その一つが「毎朝のジョギング」なのかもしれません。
毎朝の練習で5kmほど走る習慣があれば、
月2回10kmの練習を入れてハーフマラソンの本番モードに備えます。
完走できたけど、やっぱり苦しかったからもっと練習して
本番は楽に走りたいと思うかもしれません。
どうせならフルマラソンを走りたいと思うかもしれません。
そうすると、次のマラソン大会に申し込んで練習をすることになるでしょう。
ここまでくると「毎朝のジョギング」が習慣になっているので、
離脱するのにもエネルギーがいるのです。
また、大きい買い物をするという決断もエネルギーを使います。
高機能家電はわたしたちの生活を豊かにしてくれます。
例えば、ロボット掃除機は本当に高いです。
自分でやった方が早いと何度も思うのです。
自分で毎朝掃除機をかけるか?というとそうではないから、
ロボット掃除機が必要と考えたのでしょう?
実際に買ってみたら、便利なのです。
きれいな家に迎えられるという精神的安心感は何事にも替えがたいものです。
仕事をまた頑張ろうと思えますし、生活をする中でもほこりを気にせず安心して寝られるのです。
これでしっかり眠れて仕事の質が上がれば、
ロボット掃除機のお金は簡単に回収できますね。

人工芝の設置も大きな買い物となります。
「となりの人工芝は青い」ではないですが、本当にきれいですし、
うらやましい気持ちになるんですよね。
今年こそは、あの人工芝を手に入れたい!と思っているはずなのに、
体は全く動いていないのです。
大きな買い物は怖いからですよね?
失敗したらどうしよう?というのがまずあるのではないでしょうか?
わたしたち「芝人」は人工芝を敷くにあたってたくさんの失敗例を見てきました。
他社さんで失敗してしまい、それを数多く立て直してきています。
迂回するくらいなら、最初から「芝人」すればよかったのにとさえ思うのです。
それは、人工芝のことを知っているから言えることなのですけど。
芝人の人工芝を適切に敷けば10年間長持ちできます。
最近の家電サイクルと比べても長いですね。
みなさんが不安に思っていることを、わたしたちは解決することができます。
そうすると失敗する恐怖はありませんので、
安心して人工芝を敷くことができます。
あのふかふかの人工芝が自分の家にあるのです。
生活の質が3段階くらい豊になることでしょう。
きれいな人工芝に迎えられるという安心感は何事にも替えられないと思います。
「庭付き一戸建て」という夢のマイホーム
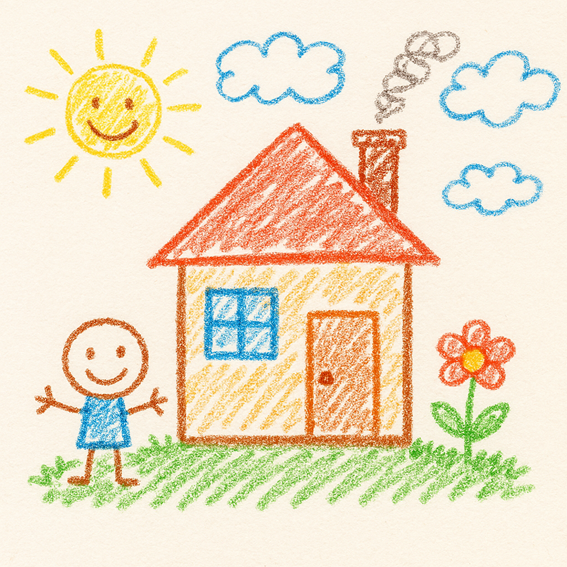
みなさんは一度や二度ならず「夢のマイホーム」ということを
考えたことがあるのではないでしょうか?
幼児が描く家の絵といえば三角と四角を組み合わされたようなものかもしれません。
それが中学生にもなると屋根の素材感を一つ一つ丁寧に描き、
庭に木が植えられ、花が咲いている様子が描かれているのです。
それらを見ていると、子供たちなりに理想の家を描いているのがわかります。
では大人にとっての「夢のマイホーム」はどんな家でしょうか?
自分の収入はさておき、描くのは自由です。
自分自身も庭付きの一戸建てを描いていたのです。
そこの庭に木が植えられていて、木陰で楽しそうに座って歌を歌っている自分の姿を描きました。
あるセッションを受けた後にまた「夢のマイホーム」を描くとまた違った絵になったのです。
使う色が増えていて、様々な色の花を庭に咲かせていました。
木というよりは樹という感じで大きく広がり根をしっかり生やした植物を描いていました。
また、家の中には自分の家族の絵を描いていましたし、
大切な動物たちも自分の家族として家の中で描いていました。
大人が描く夢のマイホームというのはそれぞれ違います。
その中で庭が占める部分がそれなりにあったわけです。
それを現実的に落とし込むために人工芝があります。
人工芝を使うことで夢の庭を現実にすることができます。
人工芝を使うことで、鮮やかな緑色の演出をすることができます。
ここを基本にして他の部分を組み立てていきます。
その上で花を植える場所を作ります。
人工芝は薬剤を使わない草対策でもありますので、
土壌汚染をすることはありません。
そのため、安全に花を植える場所を確保することができます。

【神奈川県FC:株式会社大地 施工】
花を育てるのが面倒な場合は、
人工芝だけでもちろん大丈夫です。
メンテナンス作業にかける負担を大幅に下げることができます。
日常作業でやることは掃き掃除です。
必要に応じて掃除機をかけたり拭き掃除をしたりします。
ブラッシングも定期的にやることで芝葉を元気に長持ちさせることができます。
人工芝がある場所と屋内外でつながっている場合、
靴を履かずに過ごすことができます。
室内→屋外、屋外→室内を自由に行き来できるのです。
このスムーズさが心地よく感じます。
もちろん寝てもOKです。
家の中にいるようで、外にいる開放感があるという不思議な感覚になります。
こういう感覚が夢のマイホームで手に入れたいことなのかもしれません。
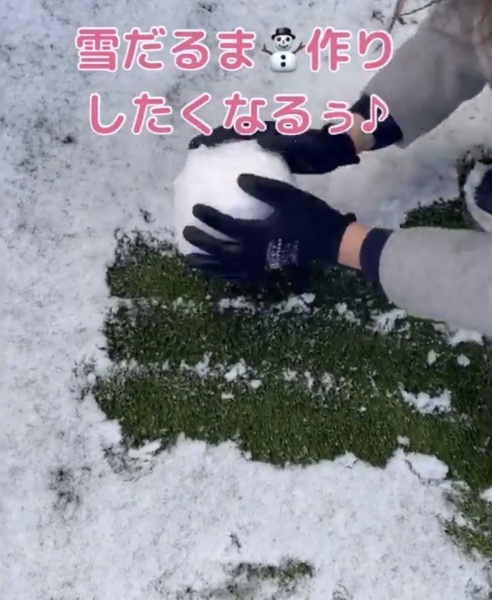

雪が降った日は自分の庭で雪だるまを作ったり、
小さなかまくらを作ったりできます。
庭付きの家だからこそできることです。
小さなかまくらでは、子供一人分しか入る場所がないのですが、
そこに入ったり出たりするだけで楽しいものです。
自分の場所ができたようでうれしいのです。
人工芝の上に積もった雪については泥の心配がありませんので、
清潔に遊ぶことができます。
細かいことですが、こうしたことも夢のマイホームには必要なことです。
みなさんにとっての庭付き一戸建てはどんな家になるでしょうか?
やってみたいことは何ですか?

こういう時だからこそ思うのですが、
これからやってみたいことはありますか?
それはどういうことでしょうか?
現実は現実として必死になって生きるのですけどね。
大きなものから小さなものまで無制限に自由に書いてみるのです。
その中の一つとして「夢のマイホーム」というのがあるとしましょう。
どんな家にしましょうか?
あくまでも「夢」のマイホームなので好き勝手書いていいですし、
書くのは自由ですし、なにしろ「無料」です。
最近知人が家を買ったのですね。
人それぞれ価値観は違います。
自分の価値観とすれば駅から近いというのが絶対条件になるのですが、
その知人はそうではありません。
電車好きの子供がいると、駅が近くて電車にすぐ乗れる、見ることができるというのが
とても大切なことになります。
しかし、知人は違います。
大切な人の家の近所であること、
学校の学区内であること、広い住居スペースがあること、公園があること・・・
そういったことが必要なことだったのです。
駅から近くなかったこともあり、
比較的リーズナブルに家を買うことができたわけです。
そして広い住居スペースがあるので、
子供部屋を独立して作ることができました。
公園が近くにあるので、ブランコに乗ったり、
砂場で遊んだり、それこそ走ったりといったことが自由にできたのでした。
スペースが広いことから、大きな洗濯機や冷蔵庫を設置することができました。
ベランダが広く、単に洗濯物を干すだけではない場所があります。
自分の夢のマイホームですから、
思いのまま好き勝手書くことができますが、
多少の参考材料はあった方がイメージが湧きやすくなると思います。
人工芝を活用することで夢のマイホームがさらに
便利で豊かになるというのはご存知でしょうか?
マンションだから必要ないと思っていませんか?
マンション生活だとしてもさらに便利で豊かな生活を送るためのアイテムとなります。

まずはベランダに敷きましょう。
ベランダに敷くとどんないいことがあるでしょうか?
まずベランダの景色が美しく映えます。
無機質なコンクリートでしたが、美しい緑色になります。2026
コンクリートの時は掃き掃除だけすればよかったのですが、
人工芝を敷くと掃除の手間が増えるのではないですか?と、
思ってしまうかと思います。
しかし、人工芝でも掃除は基本的に掃き掃除になります。
芝葉の中に入り込んだものについては掃除機を使って吸っていきます。
そうなると、思っている以上に
大きく手間が増えるようなことはなさそうですね。
人工芝を敷くとなぜでしょうか。
ついつい靴等を履かずにそのまま外に出たくなります。
そうなると
ベランダスリッパが基本的に不要となります。
このスリッパを履くという手間が地味にかかっていることに気付くと思います。
手間の感覚でいうと、洗濯時の「ジェルボール」のようなものでしょうか?
洗剤の計量、柔軟剤の計量を日頃やっている方にはそれが当たり前なので
ジェルボールにする意味がわからないと思います。
しかし、ジェルボールを始めてしまうと、
計量の手間というのはこれほど地味にわたしたちに突き刺さってきたのか?
ということを知ります。
そして、計量する洗剤には決して戻れなくなってしまいます。
ベランダスリッパを履かなくても裸足でベランダに出られるというのは、
とてもストレスフリーであるということに気付くわけです。
他にも、人工芝を使うことで便利で豊かになることはあります。
みなさんにとっての「夢のマイホーム」を作っていきましょう!
大掃除の季節です

知人が引っ越しをしました。
引っ越しというのは大変なのですが、
自分自身をリセットできるいい機会でもあります。
全てを持っていくのは大変ですから、
処分するということをします。
「ゴミ袋8袋も出た!」「ゴミを捨てに行くのが大変だった!」
そのような話を伺いました。
年末が近づいている今だからこそ、
流れに乗ってここで大掃除をやってしまいましょう。
きっかけは何だっていいのですが、
みんながやっている流れに乗るとやりやすいです。
大掃除というとどうしても「掃除」をすることを
先に考えてしまうのですが、
家の中でやることとしては「整理→整頓→掃除」の順に行います。
例えば床を掃除をしたくても
床の上が散乱していると、
拭く場所を作るためにものを動かすので非効率となります。
そのため、まず床にあるモノを決めた場所へ整理してその後、
見やすく取り出しやすくするために整頓します。
その後に掃除をします。まずは「整理」をしましょう。
これがなかなかに大変だからこそ、今からやるんです!!
人工芝はメンテナンス作業がほぼないことが利点なのですが、
大掃除をしてはいけないということではありません。
やろうと思えば大掃除をしていいですし、
大掃除をすることで人工芝をより一層長持ちさせることができます。

まずは日常の作業でもやっていることなのですが、
ゴミや落ち葉を取りましょう。
ほうきやブロワーを使ってゴミを集めてゴミ袋へどんどん入れましょう。
次からの作業はあまりやらないことになるかと思います。
掃除機を使って芝葉の間に紛れた細かいゴミを取っていきましょう。
髪の毛やペットの毛は芝葉に絡みやすいので、
掃除機を使った除去が適しています。
この掃除機なのですが、屋外用のものを使用しましょう。
コードレス掃除機は電源の確保に困らないので外の作業がしやすくなります。
次にやる作業としては拭き掃除になります。
人工芝は石油から作られた製品です。
プラスチック性の食器をこするように人工芝もこすり洗いをしていきます。
外のものを掃除しているので、あとは水でしっかりと洗い流すだけです。
最後にブラッシングをしていきます。
これは日常の作業に追加してやっていることと思います。
ふんわりと根元から立ち上げていきます。

日頃掃除しない場所をやってみると気付くことがあります。
掃除してみると明るくなったのがすぐにわかります。
それだけ日頃の汚れが溜まっていたのでしょう。
きれいな場所が放つ空気感というのがあって
それが明らかに変わります。
それこそ背筋が伸びるような感じがします。
これが年末の大掃除なのだと思っています。
年神様を気持ちよくお迎えするために、
大掃除は欠かせません。
1日でやろうとすると大変になるので、
場所を区切りながら計画的に進めていきましょう。
乾燥してきましたが人工芝ってどうなの?

平地では空気の乾燥を感じるようになりました。
というのも、自分の唇がパリッというようになってきたからです。
唇の皮のように皮膚が薄いところはこういうことでも
すぐに反応してしまいます。
この季節は大陸からの風の影響を受けます。
海から吹いてくる風は海を通る時に
海からの水蒸気をしっかり含ませることができます。
しかし、大陸からの風はそれがないので、
水分が少なく乾燥したものとなります。
その風は日本海を通過する時に水分を含むのですが、
それが日本の山を上ることで「上昇気流」となり雪雲を発生させます。
その水分は雪として日本海側で降ってしまいますので、乾いた風が平地に降りてきます。
乾燥しているか?潤っているか?の指標が
「湿度」なのですが、天気予報などで使われている湿度は
「相対湿度」のことです。
何かと比べて水分量が多いか少ないか?という数値です。
比べるもの「飽和水蒸気量」になります。
空気中に最大でどれだけの水分(水蒸気として存在している)が含まれているか?
という量になります。
これは気温が上がると多くの水分を保持できるのですが、
気温が下がってくると多くの水分を保持することができないという性質があります。
気温が下がってくるとエネルギーの高い水蒸気の形でいることができず、
水になってきてしまうからです。
そもそもの飽和水蒸気量が少ない上に、
相対湿度が30%だとしたら空気中の水分量はさらに少ないということなのです。
乾燥していることで気になってくるのが「静電気」です。
静電気はこすることで発生するというのはみなさんもご存知のことかと思います。
空気中の水分が多い時は物質表面にも水分が付着していますので、
こすって発生する電気は水へ流れていきます。
というのも水は電気を通しやすい性質があるからです。
銭湯にまれに見かける電気風呂というのは
その性質を利用しています。
その水がない場合はこすって発生する電気はそのまま残ります。
そのため乾燥していると逃げ場のなくなった静電気が
溜まってくるということなのです。

わたしたちは経験的に
化学繊維素材の方が静電気を感じるということを知っています。
天然素材は水分を含んでいるのですが、
化学繊維は石油から作られるものですから水分を含みません。
そのため、こすった時に発生した静電気は逃げ場がなく
そのまま溜まっていってしまいます。
人工芝というのは化学繊維から作られているので
静電気の影響を考えていく必要があります。
景観重視の場合はそこで何かをすることはあまりないでしょうから、
そこまで深く考えることはないかと思います。
人工芝の上で走ったりそれこそスライディングしたりするようなことがあったら、
静電気の影響は無視できなくなります。
歩いただけで「バチッ!」とくるようなことがあるとするならば、
恐怖の人工芝となってしまいます。
人工芝自体に静電気対策を施すことで、
恐怖の人工芝から安心の人工芝へ変わります。
もちろん芝人のSターフO²は静電気抑制機能付きで、耐久性にも優れてます!
静電気抑制機能が付いていない人工芝でも、
水を撒くことで静電気を水へ流すことができます。こちらの方法も有用となります。
時短テクニックは結局王道を行く

年末へ向けてどんどんせわしない空気感が出てきました。
世間全体の流れに乗っていくことで自分自身のギアが上がり、
いつも以上に作業をこなすことができるようになります。
その中でも「時短」できるものはやりたいですし、
やっておく必要があります。
え?これが時短?と思えるようなことですが、
ここをしっかりやっておくことで後々の作業が
大幅に削減できて結果的に時短になるというのが王道になります。
整理整頓や掃除をしてきれいな状態を保っておくことは
「モノを探す時間」を大幅に削減します。
平均的な「探し物時間」の目安
- 1日あたり:約5〜10分 多くの人が財布、鍵、スマホ、メガネなどを探すのに毎日数分を費やしているとされています。
- 年間:約30〜60時間 これは1日5〜10分の積み重ね。1年で丸2〜3日分を「探し物」に使っている計算になります。
- 一生で:約1年分以上 仮に80歳まで生きるとすると、探し物に費やす時間は約300〜500日にもなる可能性があります。
探し物の代表例として、鍵や携帯電話、メガネ、リモコン、書類・・・
といったものがあります。
メガネ族においてはメガネがないと見えなので、
探すことがとても難しくなります。
書類においては定期的に処分をしていかないと、
たまっていってしまい探すことが大変になります。
整理整頓をして置き場所を決めておくことがとても大切なことです。
特に、庭の手入れは作業時間が大幅にかかってしまいます。
草取り、水やりといった手間がかかってきます。
天然芝の場合は水やり、肥料やり、芝刈り
といった作業があります。
定期的に芝を刈らないと茎が立派に生えてくるので、
見た目もさることながら機能的にも悪くなります。
フカフカの緑のじゅうたんになりません。
ところどころに茎が当たってきます。
もちろん定期的に草を取る時間や
芝を刈る時間を作るということにはなるのですが、
根本的に解決することはできません。
だからこそ、もっと上流の部分で抑えることが大切です。
そもそも草を生やさない、芝を植えない!?
そこまでたどるとこれらの時間をまるごと
削減することができてしまいます。
そんなことができるのでしょうか?

人工芝を敷くことで、芝を植えない、草を生やさない
といった根本的なところで解決できてしまいます。
天然芝の替わりに人工芝を敷きます。
こうすることで見た目や機能はほぼ変わらずに済みます。
ただし、人工芝自体はピンからキリまでありますので、
高品質の人工芝に限ってしまうのですが。
これにより芝を植えなくても芝のような生活ができてしまいます。
人工芝を敷く過程そのものが草対策となります。
始めに土を掘り起こして草を全て取ります。
文章で書くとこういうことなのですが、
実際やってみるとなかなかの肉体作業です。
草の場合は木と比べると根の深さが短いので、
30cmほど掘ると根から取れます。
土を整地してその上から防草シートを敷きます。
防草シートは遮光性のあるシートのことで、
植物の光合成を遮断し、栄養分を作らせないという作用があります。
これにより栄養成分が枯渇して、枯れていきます。
その防草シートを外的環境から守るために人工芝を敷くのです。
時短テクニックは小手先のものではなく、
根本的なところから改善していくようにします。
これが結果的に大きな時間を生むので、
わたしたちが本来しなくてはならないことに注力することができます。
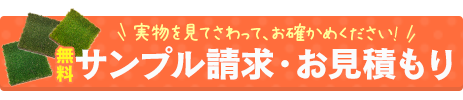
健康で快適な毎日を送るための新しい方法
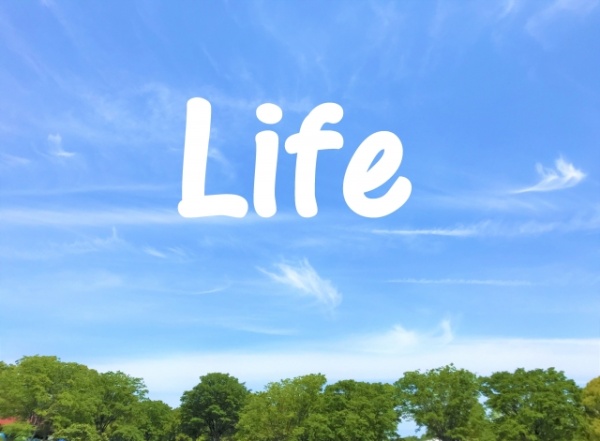
つい先日のことですが、健康診断に行きました。
食事、運動、睡眠といった基本的な生活習慣について考える機会となりました。
みなさんは健康診断を忘れずに受診していますか?
別件なのですが、「腸内細菌」についての研修を受講したのですが、
いわゆる「やせ菌」を増やすには
腸内環境をよくすることが大切であるという内容です。
これ、人工芝ブログですよね?というツッコミはさておき、
腸内環境をよくする方法としてヨーグルトでは不十分であるということなのです。
外から取り入れた乳酸菌たちは結局よそ者なので
3日ほどで出ていってしまうそうです。
自前で腸内環境をよくするためには、
食事、運動、睡眠といった基本的な生活習慣の質を
高めることだそうです。
それはみなさんもご存知の生活習慣なのですが、
野菜を食べましょう、運動しましょう、しっかり寝ましょう、
規則正しい生活を送りましょうといったことです。
生活の基盤が「衣食住」になるわけですが、
ここの質を高めることで健康で快適な毎日が送れます。
衣ですが、何もやせ見えする
ボディスーツを着ましょうということではありません。
わたしたちの体形に合った服であり、
寒さ暑さからわたしたちを守るものである必要があります。
そして、洗濯のしやすさであり、
いつでも清潔に過ごせなくてはなりません。
食においては、バランスの良い内容になっているでしょうか?
野菜は意識して取らないと足りないとされています。

そして住環境の整備です。
睡眠の質を上げるのも、
運動の質を上げるのもこの住環境が大きく関係してきます。
そして精神状態を安定化させるのも
住環境の影響が大きいです。
暗くてジメジメしているところでは
わたしたちの気持ちが落ち込んでしまうことが多いですし、
みなさんも経験として理解されていることでしょう。
住環境は健康に大きな影響を与えます。
緑がある空間は疲労回復やストレス軽減に効果的です。
しかし、天然芝は手入れが大変で、忙しい現代人にとって負担になることも。
そこで人工芝が注目されています。
いくら美しい緑を眺めてストレス軽減をしたところで、
そのための作業が負担になってしまっては
そちらの方でストレスが増えてしまいます。
だからこそ、人工芝という選択肢があります。
人工芝のメリットはこのブログでも
多々紹介しているのですが、大まかにいうと次の通りです。
- メンテナンスフリー:水やりや芝刈りが不要で、いつでも美しい緑を保てます。
- アレルギー対策:土や花粉が発生しないため、アレルギー体質の方にも安心です。
- 安全性:クッション性が高く、転倒時のケガ防止にも役立ちます。
- 季節を問わず利用可能:冬でも緑の空間を維持できるため、気分転換や癒し効果が期待できます。
また、運動する場所としても人工芝は有用になります。
クッション性に優れているので、
走ったり飛び跳ねたりするようなものでも安心してできます。
みなさんも人工芝を利用しながら生活習慣の質を高めていきませんか?
落ち葉のじゅうたんが広がります

外を見るとたくさんの落ち葉が広がっています。
これも日本の四季の移ろいを感じる風景です。
落ち葉が広がって風情ですね~と眺めているだけでは
今この現実を生きていることにはなりません。
現実問題として落ち葉の放置にはリスクがあります。
1 衛生面の問題:湿った落ち葉はカビの繁殖に適した環境となります。
ナメクジやゴキブリといった生き物が集まりやすくなります。
腐敗すると悪臭の原因となります。
2 安全面のリスク:雨で濡れた落ち葉は非常に滑りやすくなり、
転倒事故を引き起こします。
本当に滑って危ないのです。
人間だけではありません。車だって滑ってしまいます。
車が滑ってしまうと衝突事故や交通事故の原因となります。
乾いた落ち葉においては火事の火種になります。
そこに火のついたタバコを投げ入れたらどうでしょう?
たちまち火が立ち上っていきます。
3 景観・ご近所トラブル:掃除が行き届いていない印象を与え、
景観を損ないます。
掃除が行き届いていない印象があるとそこは空き巣のターゲットになってしまいます。
空き巣は家の人がいてしっかり管理されているという状況を極端に嫌うからです。
また、風で舞い上がった落ち葉が隣家に入り込むことがあります。
通行人へ落ち葉が降りかかることだってあります。
こうしたことから、「人間が生活している場所において」
落ち葉は拾わなくてはなりません。
人工芝を敷いている家庭において最もやらなくてはならない作業が
この落ち葉拾いといっていいでしょう。
人工芝は生き物ではないので、落ち葉が降り積もっても生分解することはできないからです。
葉は土に還らないのです。
それでは、人工芝の葉を傷めずに落ち葉を拾うにはどうしたらいいでしょうか?

一般的にはほうきを使って集めます。
少量の場合はそれで充分です。
落ち葉の量が多いとほうきではどうにもならなくなってくるので、
道具を替えた方がいいでしょう。
「ブロワー」という機械を使います。
風の力を使って落ち葉を移動させ集めていきます。
風の力を使うので、直接人工芝の葉に触れることはしませんから、
葉を傷めることはありません。
家庭用の小型のものでも1万円せずに買うことができます。
ブロワーを使うと腰をかがめる機会が減るので、
誰でも簡単に大量に落ち葉を集めることができてしまいます。

集めた落ち葉はゴミ袋へ入れます。
一昔前ならば、落ち葉に火をつけて焼き芋を食べていました。
落ち葉を燃やして作った熱を利用して加熱した焼き芋はやはりおいしかったように思います。
現在はそれができないので落ち葉は機械的にゴミ袋へ直行させます。
落ち葉拾いで大事なポイントが「乾いている」時にやることです。
どんな道具を使うにしてもここの大前提を抑えておく必要があります。
雨で濡れた落ち葉はブロワーの風ごときでは舞い上がってくれません。
水を含むと、とてつもなく重たくなるので、
人力を使うようなときは腰の負担が出てきてしまいます。
乾いている時に集中して落ち葉を拾うというのが何よりも大切なことなのです。

こたつから出たくない人の庭管理

気温がぐっと下がってきました。
涼しいから寒いへ変わっています。
みなさんの中にはこたつで過ごす人が出てきているのではないでしょうか?
わたしたち人間はこたつが大好きです。
こたつがあると動けなくなるのがわかるので、
あえて出さないという家庭があるのではないでしょうか?
出していないだけで本当は好きですよね?
あればこたつに入りますよね。
そして、こたつから出たくなくなりますね?
こたつは足元から暖まる暖房器具だということです。
こたつ布団で熱を効率的に閉じ込めることができますので、
あったかいのです。
頭寒足熱の理想といわれていますが、
その理想を叶えてくれるのがこたつです。
本を読んだりテレビを見たり・・・といった
リラックスタイムとの相性が抜群です。
そして、こたつの上で食事がとれるのもいいですよね。
こたつに入るととことん動きたくなくなります。
外の庭のメンテナンス作業をしている場合ではないとさえ思います。
そういう時は人工芝の出番です。

人工芝のメリット(特に寒い時期)
・寒くても美しい緑を維持することができます。
日照時間が短くても人工芝は光合成をするわけではないので、
枯れることはありません。
・メンテナンス作業が簡単です。
基本的にはゴミを取ることになります。
必要に応じてブラッシングをすればOKです。
・雨が降っても地面のぬかるみを防ぐことができるので、
いつでも清潔に保つことができます。
泥汚れを気にせずに使えます。
人工芝の注意点(特に寒い時期)
・寒さが厳しく積雪の場合、
人工芝の芝葉が雪の重みで寝てしまいます。春が来たら立たせてください。
・排水が悪いとカビが生えたり、
凍結したりしてしまいます。
人工芝を使うことで面倒なメンテナンス作業が不要となります。
1 雑草対策が不要:
防草シートと人工芝の組み合わせにより、雑草の発生を抑えます。
2 水やり・肥料が不要:
天然芝の場合はスプリンクラーで定期的に水をあげる必要があります。
また、必要に応じて肥料を撒く必要があります。
人工芝にすることでそうした作業から解放されます。
3 芝刈り不要:
天然芝の管理の肝がこの「芝刈り」になります。
定期的に芝刈りをすることでふかふかの状態を維持することができます。
芝も成長していくと茎が生えてくるのですが、
茎が生える前に葉を切り落としていきます。
上に伸びようとすると切られてしまうので、
横に広がって葉の面積を広げようとしていきます。
これにより密集した芝を作ることができます。
密集させることでふかふかの状態の芝を作っているのです。
人工芝の場合はすでにふかふかの状態で出荷されていますから、
芝刈りをする必要はありません。
これらが全て不要になるので、
外での作業を大幅に削減することができてしまうのです。
その分、わたしたちはこたつに入って暖かく過ごし、
こたつでのコミュニケーションを深めることだってできるのです。
おやつを食べながら語らい、トランプなどのカードゲームをしながら、
ともに笑ったり、年末のお庭掃除の時間削減ができます。
人工芝で心温まる時を過ごす

今年の終わりが近づいてきました。
もう、今年が終わってしまう?と気づいてしまいました。
この現代社会の忙しさで過ごしていると、
心を落ち着ける場所や時間を持つことは
とても大切なのではないでしょうか?
もちろん、自然とふれあうことは心身のリフレッシュにつながります。
しかしながら、都市部に住んでいると
本物の芝生のある庭を持つのは難しい場合もあります。
そんなときに注目したいのが「人工芝」です。
人工芝はその名の通り「人工」の「芝」です。
化学繊維を使って芝を再現したものです。
人工であるからこそ、手入れが簡単ですし、
季節を問わず楽しむことができます。
どうしても気温が下がってくると植物の生育が悪くなってしまうので、
自分が期待する見た目にならないことがあります。
それもまた自然だと考える人もいるでしょうし、
枯れてしまった風景を日々見ることで
心も一緒に枯れてくるといったことだってあります。

人工芝のある場所ではいろいろなことができます。
一人で過ごすにしても、家族や友人と一緒に過ごすにしても
それぞれの心温まる時間が作れます。
何といっても人工芝の上では
横になることができるという利点があります。
(ただし、品質の良い人工芝に限ります!)
横になって空を見上げてみるのはいかがでしょうか?
「空ってこんなに広いんだね」
「空ってこんなに青いんだね」
「雲の動きが穏やかだね」ということに気付くことでしょう。
背中には人工芝の葉が自分自身をやわらかく包み込んでいます。
チクチクするかと思いきや、ふかふかで気持ちがいいことに気付きます。
芝葉の音が思っている以上に聞こえるかもしれません。
ただただ、思いのまま感じているだけなのですが、
自分自身が無になっていくのがわかります。
無の時間が過ぎて現実に戻ると、
スッキリと穏やかな気持ちになるのがわかります。
家族と過ごすときは思いっきり遊ぶことができます。
人工芝の上では裸足になることができますので
(ただし、品質の良い人工芝に限ります!)
また違った楽しみがあります。
寒いので裸足で思いっきり遊ぶのは難しいかもしれませんが、
人工芝の上で走ったり、
ジャンプをしたり自由自在に遊ぶことができます。
クッション性に優れているので、
着地の衝撃があっても
土やコンクリートに比べて足に対する負担が減ります。

レジャーシートを敷いて食事だってできますね。
人工芝の上ならレジャーシートの汚れを
気にすることなく安心して敷くことができます。
敷いた後に泥汚れが付かないので、
そのまま室内へ運ぶことができます。
室内で食べる食事はいつも通りおいしいのですが、
レジャーシートの上で食べる食事はまた違ったおいしさがあります。
先日、子供の小学校でレジャーシートを敷いて
外で給食を食べる日があったのですが、
「楽しかった」そうですよ。
友達といい時間が過ごせたようです。
人工芝のある空間はきれいですし、
便利ですし、何しろ楽しいです。
一年中楽しめます。
現代社会でいろいろありますが、
心温まる時間は大切にしたいものです。
草に追われる日々から卒業したい

秋が終わりも近づき、植物にとっても成長していく季節ではなくなりました。
しかしながら、この秋までに成長した草はまだしっかりと残っています。
特に「雑草」と呼ばれる草たちは生命力があります。
「こんなところでも」生えるのです。
雑草といっていますが、
みなさんもご存知の通り「雑草」という品種の草があるわけではありません。
耕作地や人々が生活する場所で、
わたしたちの意図に反して生育している草のことを言います。
このような草は繁殖力が高く、あっという間に増えてしまうのが特徴です。
わたしたちの意図に反して育っている草ですから、
わたしたち人間は一生懸命取るわけですが、
すぐに生えてくるので「草に追われる」ように感じてしまうわけです。
それと同じような感覚になるのが、
日々の髭剃りでありムダ毛剃りなのではないでしょうか?
見た目をよくするために、
わたしたちの意図に反して生えている毛を日々剃ったり抜いたりしているわけです。
またそれはすぐに生えてくるので「毛に追われる」ように感じています。
脱毛サロンではそうした毛をプロが取ってくれるわけですね。
毛を生えないようにするには?毛根への処理が必要となります。

草に対しては除草剤を使って取る方法があります。
除草剤を使う方法は人体や環境への影響、他の植物への影響、
土壌の劣化など、考慮するべきことがあります。
1 人体への影響:
除草剤の霧や粉じんを吸い込むことで呼吸器系への影響が引き起こされることがあります。
また、皮膚や目に触れると刺激やアレルギー対応が出る可能性があります。
2 他の植物への影響:
目標とする雑草だけではなく、周囲の植物にも影響を与えてしまいます。
撒くときに風で飛ばされたり、誤って他の植物にかかってしまうことで、
守りたい植物まで枯れてしまいます。
3 土壌の劣化:
定期的に除草剤を使用すると、土壌の微生物や栄養素のバランスが崩れ、
土がやせていくことがあります。
これにより植物の生育が難しくなり、長期的には土壌の質が劣化してしまいます。
4 効果の持続性:
除草剤の効果が現れるまでに時間がかかることがあります。
一般的に数日から数週間かかります。
除草剤以外に「防草シート」を使った草対策があります。
防草シートは遮光性の高いシートをかぶせることで、
その場所の草の成長を止めます。
種から発芽した植物は、種の栄養を使ってある程度育ちます。
そして、葉をつけて自分で光合成をするようになります。
その頃には種の栄養分は枯渇して、
自分で栄養分を作らないと生きることができません。
防草シートはそこを利用して草の生育を抑えます。
光合成のできない草は栄養分がないので枯れてしまいます。
どの防草シートを選ぶか?についてなのですが、
これについては厚みがあり遮光性のあるもの一択となります。
「これ、手軽そう!」と安いものは選びません。
シートが破れたらそこから草が生えてくるからです。

シートを敷く際の注意点は次のようになります。
- シートの隙間や端から雑草が生えやすいので、隙間なく敷設しましょう。
- 長期間使用する場合は、耐久性や透水性にも注意が必要です。
- 施工前にしっかり雑草を除去することで、効果が持続します。
防草シート使って草から卒業しましょう!!
のっています

(※イメージ画です)
近隣のマンションでも人工芝を取り入れた場所がありました。
人工芝は手入れが簡単で、美しい緑を長期間楽しめるため、
庭やベランダ、屋上などさまざまな場所で人気です。
そのマンションにおいても美しい緑色は目を引くので
「おおっ!!」と感動していました。
円い支柱があるところは丁寧にカットされており、
上手に敷いてありました。
この円い部分を上手にカットするのが難しいのですが、
隙間なく敷くことができていました。
ところが、全体的に凹凸が目立ってしまっていて、
人工芝自体のペラペラ感をどうしても感じ取ってしまいました。
ペラペラの人工芝が「のっている」という印象を
受けてしまったのが残念なところです。
おそらく、土自体の形が月日とともに
変わってきてしまったのだと思います。
また、人工芝自体の質感や重みというのがあり、
きれいなんだけど薄いなというものだったのかもしれません。
「のっている」印象をなくし、
きれいに敷くためには敷く前の作業というのを
どれだけの精度でやるか?ということにかかってきています。
当たり前のことですが、事前準備が必要です。
それは次の2点です。
●必要な道具を揃える:
人工芝、カッター、軍手、ジョイントテープ、
U字釘、芝用接合テープ、スコップなど
●設置場所の測定:
人工芝を敷く場所の大きさを正確に測り、
必要な人工芝の量を算出します。
人工芝一つにおいてもどの人工芝を使うか?
ということを突き詰めていくとどうでしょうか?
芝人の「SターフO2」は国内で唯一無二の仕様商品で、
大変おすすめ人工芝なので、
ぜひみなさんに敷いていただきたいと思います!
景観だけきれいならいいという方には、
異なる仕様の人工芝でも十分目的を達成できる商品もございます。
芝人ではみなさんの目的をよく聞きながら、それに合わせた人工芝を紹介することができます。
カッターナイフ一つでも突き詰めていくとどうでしょうか?
わたしたちプロは切れ味を重視するために、
こまめに刃を折って新鮮な刃を使っています。
みなさんはどうでしょうか?
カッターナイフの刃を折っていますか?

釘一つでも仕上がりに差が出てきてしまいます。
人工芝を固定するためにはU字釘(角形)である必要があります。
U字釘でもリアルにU(丸形)になってしまうと固定力が落ちてしまいますし、
芝表面でデコボコしてしまうことがあります。
地面にしっかりと刺さって2本で固定できるU字釘(角形)が
強く推奨されています。
また長さと太さも固定力に関わってきます。
芝人で販売されているU字釘は、
人工芝を固定するために作られています。
そのため、芝人のU字釘を買っておけば失敗ゼロです。
芝面の土の凹凸に合わせて人工芝も凹凸してしまうので、
土づくりにもコツがあるのです。
下地づくりのコツ
- 雑草・石・ゴミの除去:敷く場所の雑草や石、ゴミをしっかり取り除きます。これにより、人工芝が凸凹にならず美しく仕上がります。
- 地面の平坦化:転圧機等を使って地面をできるだけ平らに整えます。傾斜や凹凸があると、人工芝の仕上がりが悪くなります。場所によっては重機を使うことがあります。
- 防草シートの設置:雑草対策として、防草シートを敷くのがおすすめです。端までしっかりと敷き詰めましょう。
人工芝をキレイに敷くコツは敷く前にあります。
芝人の人工芝を購入してみたものの、DIYがちょっと心配になってしまった場合は、
お気軽に芝人までご相談ください!
秋の花粉症が静かに始まっています

花粉症といえば春なのですが、
秋にも花粉症に悩まされる方が多いです。
秋の花粉症の原因植物は次のようなものがあります。
- ブタクサ(キク科):8月下旬〜10月上旬に花粉を飛ばす代表的な植物です。
- ヨモギ(キク科):9月から10月にかけて開花し、花粉を多く放出します。
- カナムグラ(アサ科):晩夏から秋にかけて花粉症の原因となります。
- イネ科の雑草:春から秋にかけて長期間花粉を放出します。
そして、花粉症ですので症状は春と同じになります。
- くしゃみ
- 鼻水・鼻づまり
- 目のかゆみ・涙目
- のどのイガイガ感
- 皮膚のかゆみや湿疹
秋の場合は風邪シーズンの始まりでもあるので、
風邪症状との見分けがつきにくく気付くのが遅くなってしまうことがあります。
のどの痛みと鼻水がなかなか治らないで、
市販の風邪薬を添付文書に記載された5~6日間を超えて飲む人がいます。
実際は花粉症なので、受診をして適切な治療を受けることが必要なのです。
秋の花粉の原因となる植物は基本的には「草」になります。
木と違って遠くへ大量に飛ばすことはありません。
至近距離を狙って飛ばしてきます。
春の花粉は爆弾を遠くへ飛ばすように攻めてくるのに対して、
秋の花粉は接近戦で攻めてきます。
基本的には「草」ですから、草対策をしていけばよいということがわかります。
このブログを読んでいるわたしたちは「草対策」を知っています。

ここで紹介されている草対策はどういうものでしょうか?
「防草シート」を使った対策となります。
この防草シートを使用した対策についてまとめると次のようになります。
1 雑草の発生を大幅に抑制できる:
光を遮断することで雑草の光合成を妨げます。
光合成のできない植物というのは栄養が作れないため、
残された栄養が枯渇した段階で生きることはできなくなります。
2 土壌の乾燥や浸食を防ぐ:
雨による土の流出を防ぐことができます。
それにより地面の安定性を保つことができます。
3 景観を整えやすい:
防草シートの上に人工芝を敷くことで見た目も美しくすることができます。
この人工芝は防草シートが日光によって
劣化していくのを防ぐことができますので、
より長持ちさせることができます。
4 コストパフォーマンスが高い:
初期費用はかかるのですが、
草刈りや除草剤を使わなくてよいので、
これらのランニングコストを抑えることができます。
耐久性の高いシートを敷くことで何年かは使用可能です。

防草シートを敷いて草の繁殖を抑えることができたら、
その上から人工芝を敷いて防草シートの劣化を防ぎます。
わたしたちはこの方法を推奨しています。
人工芝を敷くと景観を美しくすることができますし、
その上での活動もしやすくなるからです。
花粉を発生させる草がない場所で、
わたしたちは何をして過ごしましょうか?
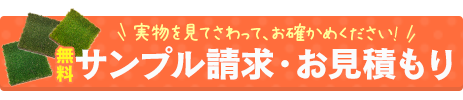
日陰だからといって油断は禁物

人工芝のある家庭は職業柄どうしても気になってしまいます。
日々人工芝に携わっているので、あの家この家とつい見てしまうのですね。
ここ数年は人工芝のよさが一般家庭に浸透してきているのを感じています。
新築の家以外でも人工芝が敷かれているのを見かけるのです。
この家はジョイントタイプの人工芝を飛び石のように使っているのかな?
この家はロール状の人工芝をきれいに敷いているけど・・・
惜しいところがある!
と、いつもやっている仕事の視点で見てしまいます。
家の周囲に合わせてきれいに人工芝を敷き詰めている家庭がありました。
最近の住宅は建物がとなり合うことが多いため、日陰になる場所ができます。
そういう場所では植物を植えることができません。
そうはいってもわずかばかりの日光で育ってしまう上に、
意図していない植物・・・雑草が生えるのです。
日陰だから大丈夫だろうと思って油断をしていると、
きれいに雑草が生えてきます。
芝や観賞用の花を植えるとなると日照時間が足りないので、
しっかり生育してくれないというのが現実です。

こうした日陰の雑草対策として人工芝を使うことができます。
人工芝は化学繊維で作られた芝生のことです。
かつては競技場で使われていたものでしたが、
一般家庭でもその技術を応用して綺麗に敷くことができます。
わたしたち芝人も競技場をメインとして販売、
施工をしてきたという経緯があるのですが、
そこから一般家庭においても販売、施工をしています。
人工芝は雑草対策になるので、多くの家庭から評価をされています。
人工芝を敷く過程で全ての土を掘り起こして雑草を完全に抜き取ります。
草だけを抜こうとすると大変なのですが、
土ごと掘って草を分けるようにして作業を進めていきます。
草なので木のように深いところまで根を生やすことはありません。
30cm程度掘り起こせば、根こそぎ取り除くことができます。
文字で書くと簡単なのですが、やってみると地道な作業になります。
それが終わると、整地をします。
この作業をテキトーにやってしまうと、
人工芝の仕上がりに差が出てしまいます。
素人目で見ても浮いている箇所が出てくるので、ケガのリスクに繋がります。
その後、防草シートを敷きます。
防草シートとは、その名の通り「草を防ぐシート」のことです。
遮光性に優れたもので、シートに覆われている部分は光合成をすることができません。
そのため、草に必要な栄養分が作れずにそのまま枯れていってしまいます。
防草シートを紫外線や雨風から守るという意味で、
その上から人工芝を敷きます。
また、シートのみの殺風景な景観を変えるという意味もあります。
緑豊かな人工芝を敷くことで、心和む景観を作ることができます。
日陰で普段立ち入らない場所にはなるのですが、
隣近所からすると見えてしまう部分にはなるので、
美しい状態で保つということがとても大切です。
人工芝ならば、お手入れが簡単できれいな景観を保つことができます。