日本の車窓から

休日を利用して電車に乗って遊びに出かけた時のことです。
普段乗らない電車からの車窓はとても新鮮でずっと眺めていられます。
流れる景色を眺めながら、その土地ならではの
風景や季節の移り変わりを感じるのはとても贅沢な時間ですね。
今回走っていた場所は電車の開業とともに新しく切り開いた街になります。
大型のショッピング施設が立ち並び、高層マンションが集結しています。
整然とした街並みが続いています。
そして、公園があり憩いの場所として機能しています。
マンションの先には抜けた青空が続いています。
この沿線は住環境のよさと都市部へのアクセスのよさから人気が出ています。
鉄道沿線の雑草管理は、安全性や景観維持のために重要な作業となります。
新しく作られた鉄道ですので、「草が生えたら刈り取ればいい」ということではなく
効率的な方法を導入し作業負担を減らしています。
より良い方法により環境への負荷を減らすことができます。

(※イメージです)
車窓を眺めながら気づいたのが一面の防草シートでした。
一昔前の鉄道ではこのような風景はありませんでした。
それこそ、ススキが生えていたり、
ブタクサが生えていたり、ハルジオンが生えていたりしていたのです。
それも含めて車窓でした。
一面の防草シートにより草がなくスッキリとした車窓に変わりました。
どこか無機質な印象があったのですが、
それは一面のシートが続く異質さにあるのかもしれません。
防草シートは雑草の成長を抑えるために地面に敷くシートのことです。
遮光性が高く、雑草の光合成を防ぐ仕組みになります。
種子から発芽した草は、しばらく種の栄養分を使って成長していきます。
そのため光は必ずしも必要ではありません。
しかし、光合成によって栄養分を作っていかないと、
種の栄養分が枯渇した段階で栄養分がなくなります。
栄養分が作れなくなるので草は成長できずそのまま枯れてしまいます。
それを利用して草対策をしています。
除草剤による方法と違い、土への環境汚染がなく
周辺への影響を抑えることができます。
このシートは「遮光率」が最優先となります。
せっかく敷くのですから、シートを突き抜けて草が生えてきたら
意味がないのです。遮光率の他に注意するポイントは次の通りです。
1 耐久性:
せっかく敷いたものがすぐに劣化してしまっては
ランニングコストが上がってしまいます。
紫外線や摩耗に強いものを選ぶ必要があります。
2 水はけ:
透水性があると水がたまりにくく、
細菌やカビの発生を防ぎます。
また水たまりができてしまうとそこを起点として蚊が大量に発生します。
3 設置方法:
シートの端から光が差し込みやすくなるので、
隙間ができないように敷いていく必要があります。


(DIYお客様ご提供画像)
家庭で使用するときは、防草シートの上から人工芝を敷くようにしましょう。
シートの劣化を防ぐのが大きな目的となります。
その他に、無機質な印象ではなく温かい印象を与えますし、
人工芝の上で活動をすることができ土地の有効活用に繋がります。


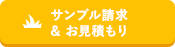
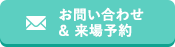



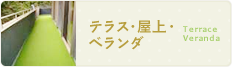
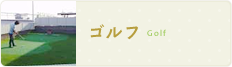
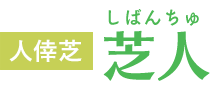





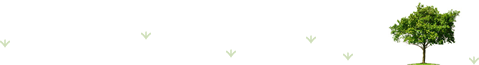

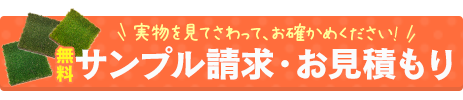
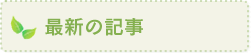


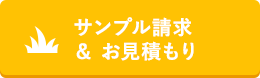
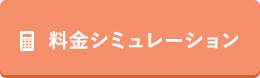
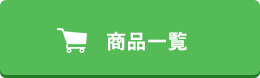




コメントを残す